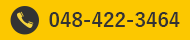株式会社セイリョウ【小林隆文社長インタビュー】
株式会社セイリョウの代表取締役社長である小林隆文。
スタッフと共に汗水流して働きながらも、社会情勢にアンテナを張り、会社を日々成長させてきた。
小林社長の考えや願いを存分に語ってもらうコーナー。
(外部ライター取材)

目次
◆いよいよ開始2024年問題
◆セイリョウのピンチ
①2023年、年末に起こった大事件
②それでも残ってくれた光
③泣きっ面に蜂、さらなる追い打ちとなる出来事
④株式会社セイリョウの魅力を発信する
⑤マイルールに縛られていた現状からの脱却1
⑥マイルールに縛られていた現状からの脱却2
⑦マイルールが作られてしまう人材の傾向
⑧ルーティーン化することで強い企業に
◆社長の人生と会社の人生
◆2024年を振り返る
◆2024年最後に起こったターニングポイント
◆退職代行を使う世の中について
◆外国人労働者雇用
いよいよ開始2024年問題について①
※『2024年問題』とは、運送業界は2024年4月から時間外労働に対して、
上限が年間960時間に制限され、それに伴い発生する問題の総称
Q、2024年4月から行われる
運送業界時間外労働時間の制限の話を聞いた時、社長は率直にどう思いましたか?
小林「これは『チャンス』だと思いました。
その理由は、うちはその準備ができていると思うからです。
過去には労働基準監督署に駆け込むスタッフがいて、
その都度そういう対応して改善を図ってきました。
株式会社セイリョウは運送業界にとって、
大変非常識な労働形態に変化したんだと思っています。
運送業界は時間外労働をしてなんぼの世界です。
それをうちではやらずに、
もしもそれを期待して入社しようとする人がいてもお断りをしてきました。
仕事ばかりの人よりも、
生活を充実させたいという人を集めてきたんです。
ドライバーや運送を行ってきた人の中にも、
必ずしも長時間労働で稼ぎたいという人ばかりではないということです。
そんな方々が働きやすい労働環境をつくってきました」
Q、2024年問題に直面した時に、株式会社セイリョウでは何に取り組んでいこうと思いますか?
小林「より人材採用に取り組んでいこうと考えています。
2024年問題が出てくる前から、
シェアを広げていくこと、労働環境を整えていくことをしていました。
そうすることによって、
今まで運送業界にはいなかった人材の入社希望者が増えてきました。
例えば60代以上の高齢者の方やWワーカーの人たちです。
今までの仕事を1人で全て行わずに、
1.5人~2人でやるという発想に切り替えていくことが大切になっていくと思います。
そうすると人が取れる会社が生き残っていくと思うんです」
Q、具体的な数字として何人ほしいですか?
小林「10人以上です。
コロナが落ち着いて、
今まさに仕事がどんどんとれる時期になってきています。
しかし、荷物を持っているお客様が、
それについてこられていない状況です。
いままで通りに業者が見つかるだろうと思っていても、
こんなに物価が上がって、ガソリン代も上がってしまったら、
今までのような賃金ではやっていけない状況です。
しかし、お客様はその荷物はどうにかしないといけない。
だから思いのほか運送会社側の言い値が叶ってしまう現状になっています。
そうすると、やはりどんどん人が欲しいですよね」
Q、より人材を入れていくにはどのようなことに力を入れていきますか?
小林「株式会社セイリョウは社風のいい会社ですよ」と
もっと露出やアピールをしていきたいと考えています。
HPの事例記事を豊富にしていったり、
SNSも発信していったりして、
社内を見てもらうことに力を入れていこうと考えています。
いくら求人で
『働きやすい会社ですよ』『アットホームな会社です』と謳っても響かないですからね」
Q、事例の記事を読まれているという感触はありますか?
小林「手ごたえはありますね。
本気で入社を考えている方はもちろん、
若い方は結構読んでいます。
『書かれていますよね』というお声を聞きますので。
若い人はインスタがきっかけで、
HPに入ってくるという流れです。
まさにそういう時代になってきたんだなと思っていますし、
2024年問題は、そういうのも駆使してチャンスをものにしていく時だと思っています」
【小林隆文社長インタビュー】いよいよ開始2024年問題について②
※『2024年問題』とは、運送業界は2024年4月から時間外労働に対して、
上限が年間960時間に制限され、それに伴い発生する問題の総称
Q、小林社長はこの政策を「チャンス」と言いましたが、政府のこの考えは良いものと思いましたか?
小林「いや、まったく思っていません。
現状を全く理解していないですよね。
僕のような考えでやっている社長さんがいっぱいいれば、
この政策はチャンスになるのですが…。
だから同業の中に今回の政策をきっかけに廃業するか、
Ⅿ&Aをするかと岐路に立たされている会社が出てきました。
業界の中の人の常識やレベルを政府は理解していないなと感じました。
ただ、うちはやはり勉強しているので、
それをチャンスと感じられているんだと思います。
見えないところを…
まさにインナーマッスルをコツコツと
鍛えるように整えてきました。
ただ売り上げやひたすらに
物を運ぶことだけに重きを置いてきた会社は、
この政策はピンチだと感じていることでしょう」
Q、小林社長は実際に同業者の方からどのような声を聞きましたか?
小林「弊社のようにインナーマッスルを
鍛えてきた会社の社長さんは、
割と対岸の火事のような感覚で観ている人が多いですね。
『俺らは関係なく前に進んでいるよ』という感じで。
でも逆に学んでない、勉強していない方たちは結構苦しんでいると思いました。
仕事を削り、減車をしないといけない。
『(こんな状態での)運送屋ではやっていけない』ということをちらほら聞きます。
あと、会社を売る方が結構いるんですよね。
うちの規模よりも大きな会社が、そういうことをし始めているんです。
要するに、この現状の中で会社の未来を見据えられず、
あきらめてしまったんだと思います。
長時間労働をしないとドライバーの給料を払えないという思考に
縛られている社長さんは一生そのままですからね。
2024年問題が分厚い壁にしか見えていないと思います」
Q、思わぬ痛手を負ってしまった場合どうしますか?
小林「あまりそのようなことは考えていません。
やっぱりチャンスということでしか考えられないですね。
今までうちがやろうとしてきたことを、
国が後押ししてくれていると考えています。
そもそも、なぜ平気で13時間働かせられるの?
と疑問に思っていましたが、
業界ではそれが当たり前に根付いてしまっていて、
特例とされてきました。
やはりちゃんちゃらおかしな話だったんですよ」
Q、それでは不安はないと?
小林「強いて言うなら『自動運転の発展』ですかね。
しかしそれも、すぐに発展したとしても、
大型車からの導入の可能性が高いです。
もし、弊社が主に使っている2tトラックにまで自動運転の波が来た場合は、
何か対策を考えないといけないなと思っています」
Q、政府が掲げた政策によって、運送業界はどのような方向に進んでいくと思いますか?
小林「まず自動運転が発展していくとは思うのですが、
それ以上に運送業で働く人が減っていく現状になっていくと感じています。
理由は今のどの世代でも、
運送業になりたいっていう人が少なくなってきているからです。
運送業に限らず、ブルーカラーの職業になりたい人が減ってきていますね。
サービスはほしいけどやりたい人がいないという現状です。
それが今よりももっとひどくなっていく。
そうなると、その業界の価格が上がり、
価値が付いていくと思います。
『では、より新規参入していくんじゃないか?』
と思われると思うのですが、
より一層人は取れなくなってくると考えています。
なんとなく、今の若い子の働くマインドがデスクワークに行きがちです。
いろんな業界の人と話しますが、
どこも『うちの業界は人気がない』と口に出します。
どの業界もだと、
いったいどこに人がいるんだ?と疑問を持ってしまいます。
やっぱり中小企業のブルーカラー職じゃないところに人は
集まってきてしまっているのが現状です。
業界が人材不足になったら、
先ほど言ったように価値が上がってきますので、
生き残りさえすればより価値を上げて利益をしっかりと取れると思います。
これから生き残り戦略をしっかり立てることが大切です」
株式会社セイリョウのピンチ
①2023年、年末に起こった大事件
大量離職
2024年問題を目前に、株式会社セイリョウではその政策に向け、準備をしていました。
とは言っても、
弊社では、以前から2024年問題のようなことがあっても
耐えていけるようなシステムを構築していたので、
何も問題を感じていませんでした。
あとは2024年を迎えるだけと思っていた矢先、
大きな出来事が株式会社セイリョウを揺るがします。
それは前代未聞の大量離職です。
始まりはベテラン事務スタッフが急に退職を願い出たことからです。
理由は家庭の事情で仕事はできなくなってしまうという内容でした。
その後、そのスタッフと仲がよかった新人スタッフが退職願いを提出、
さらに新卒の若いスタッフが5人中4人退職届を提出してしまいました。
これからの株式会社セイリョウを背負っていける力が、
一気に失われてしまった瞬間でした。
表には見せなかった裏の顔
これは何かあったのではないかと思い、
そのベテランスタッフ退職後に、既存スタッフにヒアリングを行いました。
そうすると、ベテランスタッフの表には見せなかった、裏の顔を知りました。
例えば仕事をお願いすると、
表では「やります」と言っていたのが、
実際はやれていなかったということ。
そして、上司がいない場所で不の態度を露骨に出していたようだったのです。
そして、その裏と表の使い分けがすごく上手だったため、
社長や幹部は気がつくことができませんでした。
振り返ってみると、
確かに「あれ?」と思うシーンはありましたが、
些細なことだと思い、スルーしてしまっていました。
それをスルーせずにしっかりと向き合っていればよかったのかもしれません。
そして、それが若いスタッフに少なからず影響していたようです。
その人が発する愚痴に左右されてしまい、
周りのスタッフ、特に若いスタッフも気持ちが持っていかれてしまったようです。
そのベテランスタッフが辞める際、
若いスタッフに伝えた一言があります。
それ聞いた時、私はすごくショックを受けました。
その言葉とは「頑張ったけど、私が会社を変えられなくてごめんね」という言葉です。
たった一言だったけれど、大きな影響を若いスタッフ達に与えたなと思います。
この言葉を聞いた若いスタッフ達は次々と辞めていってしまいました。
この言葉を聴いて、若いスタッフはどんなことを思ったのだろう…
と今でも考えてしまいます。
ベテランだからとスルーしてはいけない
思い返せば、無意識にサインのようなものを送っていたのかもしれません。
それを私たちは「ベテランだから」「いつものことだから」と
“いつもの景色”と思ってスルーをしてしまっていました。
日ごろから常にマイナスな言葉を使う人には、
注目しないといけなかったのだと後悔しました。
そういう人は、
実はかなり深刻な状況だったと気がつかなければならなかったのだと。
そしてその深刻な状況は、
周りにも伝達され、知らぬ間に大変な状況まで傾くのだと思い知らされました。
雰囲気にのまれて同調
ベテランのスタッフが徐々に見せてきた、
小さく不可解な行動。本当に些細で日常的なものだったからこそ
「ベテランのあの人なら大丈夫だろう」「いつものこと」と思い、
スルーしてきてしまいました。
また、周りもその雰囲気にのまれ、
深く考えず、同調するようになってしまっていたようです。
意見に従わなければ何をされるかわからないという、
雰囲気が作り上げられてしまっていたように感じます。
肯定的な否定
やはり会社としてやってはいけない態度を、
本人としっかり向き合い
注意してかなければならなかったのだと反省しています。
誰にも言われなかったからこそ、好き勝手にやってしまったのだと思います。
必要だったのが「肯定的な否定をしていく」ということです。
問題点を肯定してそれを治させていく、
治すことができるように
促していくということが大切だったと思いました。
そして、しっかりと会社の価値観を共有し、
気持ちを変えてもらうことが、
組織内で働くために必要なことだと思いました。
入社の入り口を考え直す
株式会社セイリョウが今の状態になる前、
まだ“運送業のうんちゃん“のような会社をしていたころ、
今以上にたくさんの人材が退職していきました。
離職率は今よりも格段に上でした。
出ていってしまった分、
補充しないといけないため、
人数合わせ、
働く人の手をとにかく確保しないといけないため、
どんな人でも入れていました。
そのため、お金をもらえればいいという人材もどんどん入ってきました。
会社内の個々の目線はバラバラです。
その影響が、今回まで引きずり大量離職に繋がりました。
今後は、入社させる人材をしっかりと選定しないといけないのだと思いました。
「僕はやめる気はないです」
新卒で入社した若いスタッフが軒並み辞めてしまい、
残ったのはたった1人です。
その1人は本当に仕事がうまくいかず、どん底を経験しました。
社長の私が何度も注意をして、
どうして注意されたかを
課長が一緒に面談などで振り返りをしていきました。
その回数は実に41回。
そこまでいってしまったら、
逆にやめたくなるのではないかと思われるかもしれませんが、
彼はその分考える時間が多くなったため、
会社の価値観や自分が何をしなければいけないのかということを、
じっくりと見つめることができたようです。
そして、自分以外の新卒が辞めてしまった直後、
彼は私と新人育成チームのスタッフに
「僕はやめる気はないです」と言ってくれました。
今まで株式会社セイリョウでは
新卒のスタッフを中心に新人育成の研修を行ってきました。
それがしっかりと実ったのだと思い、
小さな光を感じることができました。
一筋の光を感じながらも、
これから辞めていってしまったスタッフの分を補うために、
人材を募集しなければなりません。
しかし、思いがけないピンチはこれからも続きました。
続くスタッフの退職
昨年末に起こってしまった大量離職。
「何とか残ったスタッフでやりくりをしていかないといけない」
と、日々考えていました。
スタッフに、より強い負担を与え過ぎないように、
しかし、利益を損なわないように、と考えを巡らせ、
スタッフ配置の変更も視野に入れていました。
とある入社1年目の事務スタッフに
部門異動してもらおうと思っていました。
そのスタッフは、頑張って日々業務をこなしてくれていたものの、
能力が追いついていないのではないかと判断し、
今回の考えにいたりました。
そう思っていた矢先、思いがけない言葉をそのスタッフから聞くことになります。
突然、そのスタッフから、
退職願いを出されてしまいました。
今までのように、能力の向上を臨んでいたため、
きっと苦しくなってしまっていたのだと思いました。
心が乱れる時
つくづく人材育成というのは難しいと感じました。
違うポジションであれば、
今よりも苦しくなくやっていけるのではないかと思っていましたが、
本人の中で気持ちは決まっていたのでしょう。
私も、昨年末の大量離職からなんとか気を取り直して頑張っていこうと思った矢先、
このようなことが起こってしまい、
いつもなら「こういう時は変わっていく時、変化していく時」
と前向きにとらえられるタイプなのですが、
感情が追いついていかず、心が乱れてしまっています。
こういう時は事故も起こしやすくなるので、
気をつけないといけないと思っているとこです。
入ってこない応募
昨年末から今年2月にかけてスタッフの退職が相次ぎ、
心も少し乱れてしまっているこの頃ですが、
そうクヨクヨしている場合ではありません。
人材は、すぐさま補充しないといけません。
いつものように、すぐに求人を出しました。
それは昨年末に引き続き行っていることです。
しかし、以前に比べて応募が少ない、
むしろ、応募がないに等しい状態です。
これはどこも人材不足に陥り、
他の企業も求人募集(求人広告、求人サイトへの載せ方)
について研究し始めたためであろうと考えています。
株式会社セイリョウが今まで行っていた求人への工夫が、
いよいよ通用しなくなってきたのだと思います。
人材確保のために…
今後も、株式会社セイリョウでは求人を出して人を呼び込もうと思っています。
しかし今までのやり方では何も進歩がありません。
そこで考えたことは「より目立つことをする」ということです。
もちろん、安直に目立つ広告を出す、
というわけではありません。
いろんなところに出向いて、
株式会社セイリョウにどんどん興味を持ってもらおうと考えています。
大切なのは株式会社セイリョウで何ができるか、
何が魅力かということです。
その魅力を存分に発信していきたいと思っています。
運送業を通して人材育成をする会社
大量離職に伴う人材不足を補うために、
求人ではより目立つことをしていこうと考えている現状。
それは目立つ広告を出すわけではなく、
新卒採用を狙い、少しでも株式会社セイリョウに興味を持ってもらうことです。
そこでより強調して発信したいと考えていることは
「運送業を通して人材育成をしていける会社」だということです。
運送業という職種は、
まだまだ“トラックの運ちゃん”の印象を拭えません。
さらに中小企業では、
仕事をして利益を出してくれればそれでいい、
日常の業務内では利益を出すだけで精いっぱいだと、
丁寧に会社の研修やマナーを教えるということはあまりありません。
大企業に入らないと、そのような人材として成長できない、
勉強できないというイメージがあります。
そんな中で、運送業で社会人のマナーや仕事をする上での心構えが学べる
入りやすい中小企業だと発信していけば、
より意識の高い人材の確保ができるのではないかと考えています。
何をしにここに来たかがわかる人
なぜ、就職するのか、就職しなければならないのか。
その理由は人それぞれですが、
今まで株式会社セイリョウに入社してくれたスタッフを見ると、
長く続けてくれたスタッフ、すぐにやめてしまったスタッフ、
それぞれの考え方の傾向がわかってきました。
もちろん必ずしもそれに当てはまるわけではありませんが、
長く続ける人は
「ここに何をし(学び)に来たのかがわかっている」ということです。
そしてそれが日常の節々の言葉からもうかがえます。
そのようなスタッフは会社で起こることを自分のことのように話します。
「〇〇なことがあったんだよ」
『それじゃあ▲▲して直しいかないとダメですね。自分も気をつけます』ととらえます。
このようなスタッフは会社にとって、とても大切な存在になります。
しかし、なんとなく仕事を決めてきたという人は、
言葉の節々にどこか他人事ということをうかがえます。
しっかりと人材を厳選すること
以前は、後者のようなスタッフもかまわず入れていましたが、
長く務めてもらうためには、弊社の経営理念を知ってもらい、
それに賛同してくれる人を入社させることが大切だと思いました。
残ってくれた従業員の中で「僕はやめませんから」と言ってくれた子のように、
経営理念を理解し、弊社の考えに賛同してくれるスタッフで、
より新しい株式会社セイリョウを作っていきたいと考えています。
新しい方の入社
大量離職があった期間から、約5カ月が経ちました。
新しい人材が株式会社セイリョウに入社し、少しずつ社内が変化しはじめてきました。
結論から言うと、すごく良い方向に向かっています。今回そのお話をさせていただきます。
人の移り変わりが激しい中で見えてきたこと
大量離職の中心に立っていた配送事務のスタッフがいました。
仮にそのスタッフをAさんとします。
Aさんは週5で入っていて大変スピーディーに仕事をこなす方でした。
ミスもなく、仕事をしていたので、たくさんの方から信頼を置かれていました。
そのスタッフと、
そのスタッフの後に入社した週3で仕事に入るBさんがいました。
Bさんは後にAさんより、仕事の引継ぎをされます。
しかし、他人から見ても、これを週3のBさんが全てをこなすことは無理です。
もちろん、スタッフ募集をかけます。
それと同時に、業務を見直し改善をしていくことも行いました。
Aさんから引き継いだ莫大な業務内容の中には、Aさん独自のルールがありました。
そのAさんのマイルールは、正直やらなければやらなくてもいい内容だったのです。
しかし、昔からやっていることだったり、Aさん自身がそれをやることによって、
業務のやりやすさを感じたりして、余計な仕事もマスト業務だと思ってやっていたようです。
もちろん、そのAさんのマイルールもBさんの引継ぎの中に入っていました。
そのマイルールがそのまま伝わってしまったことにより、
Bさんは全く仕事が終わらない上に、ミスも多くなりました。
これを改善しようと、業務見直しをBさんに掛け合ったのですが、
ずっとそのマイルール付きの業務をしていたので、
それで定着してしまい、変えることができないと言われてしまいました。
新たに入ったCさんとDさん
大量離職で至急開始した求人に、Cさんが入社しました。
新しく入社したCさんは週3での勤務になります。
しばらくBさんとCさんでAさんがやっていた仕事をしていたのですが、
その後にBさんが全く別の理由で退職することになりました。
Cさんがひとりになってしまうというところで、
Dさんが入社してくれました。
そのDさんは週5で18:00までの勤務です。
本当にありがたい人材だと思いました。
配送事務のメンバーが一新したので、
ここで業務の見直しができる大きなチャンスができました。
後に入ってきたCさんは、
配送事務の現状を見て
「変えていきたい」「改善した方がいい」と考えていたそうです。
新たに入社したCさんとDさんとともに、
話し合いをしました。
そして、いらないルールを省いたり、
やらなくていい仕事を見直したりして、
以前の「会社としてやってほしい業務内容」だけにすることにしました。
すると、1つの業務にかかる時間が少なくなり、
大変スムーズな仕事の運びに改善しました。
不要なマストを作って人に強いていた
会社が指示していたのは、必要最低限の業務でした。
しかし、それ以外のことも必要と感じ、
やらなければやらなくても良い業務をマストの業務だとして、
マイルールを作ってしまったAさん。
Bさんと一緒に仕事をしていた時、
そのマイルールも、Bさんに強いていました。
そのマイルールはAさんが必要だと思って、
Aさんが始めたことなので、
Aさんの能力値の中でやる分にはいいのですが、そ
れを人にも強いてしまうと、強いられた人の能力値に合わず、
業務のミスや遅延が起こってしまいます。
現にBさんがそうでした。
実は別の古参のスタッフも、
その業務を行っていたことがあったのですが、
その際にはそんなに大変な作業だとは思わなかったそうです。
僕自身も新しく入社した人に
「配送事務は簡単な作業だから」と話して、
業務に就かせていたのですが、
そのAさんが「簡単じゃないですよ!」と言いました。
そして、その反応に対し、
「そんなに大変なのであれば業務を見直そうか?」と話しをすると
「社長はわかっていない」と言われ、
見直しの方向へ進むことができませんでした。
そして今、スタッフが一新した配送事務は、業務を見直すことに成功しました。
現場でも起こっているマイルール
今回のようなマイルールは配送事務に限ったことではありません。
ドライバーの現場でも起こっています。
例えば8時間で終わる仕事が、
朝3時~14時までかかってしまう人がいた場合、
だいたいはいらないマイルールを作り、
仕事が終わらないということが多々あります。
中小企業の悩みのひとつなのですが、
このような生産性の低さに気がついても、
人手や時間により手を加えられることは難しいのが現状です。
なので、マイルールを作っても、
仕事を回すことができる人を大事にしてしまいます。
1日やれることを細分化、どんな方でもできる仕事内容
そこで、セイリョウでは仕事を、
細分化して見えるようにするということをし始めました。
そうすることによって、
その仕事は誰かにしかできないという状況をなくすことができるのです。
それをすることによって、誰かが休んでも、
その日は別の人がやればいいという様態です。
そのためには、マイルールはなくさないといけません。
もともとは2008年に作ったマニュアルがあります。
それを見て少しの指導時間を用いれば誰でもできる様に
作った内容なのです。
新たにマイルールを作らないといけないと
終わることができないという仕事ではないのです。
2008年に作ったそのマニュアルは、
誰でもできる安定した仕事の仕組みを元に作られたものです。
そのマニュアルでどんな方でも仕事ができる環境が成功していくと思います。
Yesマンは有能
昔は、会社が言っていることを聴く
「Yesマン」はダサいと言われていた風潮がありました。
しかし、今回のように生産性の低いマイルールに、
自他ともに縛られてしまう人よりは、
会社が指示したことを素直に行ってくれるYesマンの方が、
やはり会社としてはありがたい存在だと思います。
そのいい意味でのYesマン、
すなわち会社の方向性を理解しているスタッフさん達が増える事が
会社の利益を生み、
会社を育てていってくれるのではないかと考えています。
管理職の暴走
株式会社セイリョウで起こってしまった、
古株のスタッフによるマイルール作り。
会社のルールがしっかりとあるにも関わらず、
さまざまな理由を付けて、
そのマイルールで仕事をするということが起こっていました。
これは何も株式会社セイリョウだけが
特別に起こったことではないということがわかりました。
他社の幹部の人と話をすると、
同様のことが他企業でも起こっているそうです。
このマイルールが作られ、
本来の会社のルールがわからなくなったり、
企業がうまく回らなくなったりしてしまうことが多々あると聞きました。
特に多いのは管理職が自分の地位を使い、
簡単な方に業務を進める
マイルールを作ってしまうということです。
この管理職の暴走により、
業務の生産性が落ちたり、
成績が上がらなくなったりすることがあります。
しかし、なぜそうなってしまうのか、
結果が伴わないのか、
その原因が実は管理職のマイルール作りが
原因だということの発見に至らないことがあります。
そして気が付けば、
全体の統率が取れなくなってしまうということがあります。
どれが正しいルールなのかが見えなくなってしまい、
社内は混乱の渦になります。
決めたルールを守れなくなってしまったら、
組織はダメになってしまうのです。
声が大きい人に寄っていく傾向
このようなマイルールを作ってしまう人の傾向として、
自分の意見をはっきりと言う、
声の大きい人が多いイメージです。
そのような人の周りには人が寄ってきます。
なんとなく「あの人が言っているから正しいのではないか」と
その人へと寄っていきます。
中には、会社のルールをしっかりと見据えて
「会社のルールはこっちだ」と
疑問を持って仕事をしている人もいました。
しかし、その人も決して声の大きい人ではなかったので、
会社のルールを守りつつ、
マイルールでやっている声の大きな人の方にも
気をつかいながら仕事をしていました。
正しく仕事をしている人には余計な負担をかけていたと思います。
マイルールができた時にわかる要素
マイルールで業務をしていたスタッフがいたことは事実でした。
今思い返してみたら、
要所に「あれ?」と思うシーンがいくつもありました。
完全に隠しきれていなかった表情やしぐさが、
実は垣間見ることができた場面があったのです。
しかし、誰も疑問に思いませんでした。
「あの人なら大丈夫だ」「あの人のことだから心配ない」と
思い込んでいたのです。
株式会社セイリョウのルーティーンの中には
それがわかる要素がちりばめられていると思いました。
朝礼や会議、委員会活動など、
通常業務以外にもさまざまな業務を行っています。
そうすると、
「朝礼の時の言動が変だった」
「あんな答え方をするということは
会社が提示したやり方に沿ってやっていないんじゃないか?」と
疑問に持つことのできるチャンスが多々あります。
あとは、
スタッフや上司がそれに気がつくかどうかなのだと思いました。
ルール以外は強制させない
マイルールを作って仕事をしていた件に限らず、
「あの人最近おかしいぞ」と
気がつける環境かどうかの中に「強制感」というのがあります。
株式会社セイリョウは1日の仕事に対して、
あまり強制感を与えるということはありません。
もちろん全て自由にしていいというわけではなく、
会社のルールに則って業務をし、
ある程度の節度を持って
過ごしてくれればそれでいいとしています。
そのくらいシンプルな考えで、従業員に接しています。
厳しい会社にあるような、
何にでも強制をさせてしまう環境だと、
人はその場を凌ぐために隠したりいい顔をしたりします。
それによって、正しいことが見えなくなってしまいます。
シンプルな考えが、
さまざまな歯車の軋みを感じとることができるのではないかと思います。
マイルールを作る人の癖
マイルールを作りがちな人は、
与えられた仕事を自由にやりたいと考える人だと思いました。
というのも、業務を仕組化する際に、
必ずその人に反対されていたのです。
「ルーティーンにするために仕組化した方がいいよ」と
会議で話をしても「いや…」と反対されてきました。
マイルールを作る人は、
ルーティーン化されることを嫌います。
そうしてしまうと、自分のやり方で自由にできないからです。
しかし、それを許してしまうと、
困ったことに、他の人にもその業務を引き継ぐことができないのです。
そして、相談の仕方も違います。
例えば、どうしても業務が終わらず、
引継ぎをしないといけない場合、
しっかりルーティーン化したやり方で
業務をこなす人はできていない業務の内容も明確で、
お願いされた方も
その手順に沿ってやっていけば終わります。
しかし、マイルールでやっていた人は、
まず説明が長く、どこかふわふわした状態で業務を投げ、
頼まれた方も何をすればいいかわからずに
業務が完了しなかったということが多々ありました。
自由に業務をしたいという甘えで、
円滑に業務を引き継げるのかどうかの差も生れてしまうのです。
ルーティーン化によるデメリット
ルーティーンによる仕組化をしたことにより、
デメリットも生じます。
それは緊急対応や臨機応変な対応を求められる際に、
すぐに対応できなかったり、
完了まで至らなかったりすることが出てきてしまうということです。
今はルーティーンに沿って
仕事をこなすメンバーで頑張って業務をおこなっているので、
トラブルや臨機応変に対応しなければならないことに関しては
得意ではないと思います。
そういうことは僕に集まってきてしまいます。
今後、臨機応変に対応できる組織になる為には、
徹底的なジョブローテーションを行う必要があると考えています。
ひとつのポジションだけではなく、
期間を決めていろんな部署を体験させるということです。
各ポジションのルーティーンを身体にしみこませることによって、
その部署の人がいなくとも業務が滞らないようになると思います。
万が一、僕が明日から入院してしまう、
なんてことが起こっても、
トラブルの対応もしっかりとできる、強い組織になっていくと思います。
その中でも得意不得意があるので、
得意なことを見出して伸ばしていき、
不得意なことはそこそこできるようにする。
そこまですれば、十分なのではないかと考えています。
社長の人生と会社の人生
-2014年の振返り-
【さあ頑張るぞと思った矢先の第2回大量離職】
2014年3月ごろに、外部研修の企業と出会い、経営のあり方、会社のあり方を学び
「さあこれから頑張っていくぞ」と思った矢先、同年12月でした。
幹部のひとりである、僕の弟が「辞めたい」と言ってきたのです。
明確な理由はわかりませんでした。
しかし、母の逝去、家庭内のいざこざが重なり、
社内の少しの不安でさえも大きなストレスに感じていたのでしょう。
当時、弟も研修へ行く段取りを組んでいたので、その急な申し出に本当に驚きました。
母親も亡くなった矢先でもあったので、
まさかこんなにも人を失ってしまうのかと本当に悶えました。
その時の心情は-10です。
さらに弟は幹部です。
弟を慕っていた多くの従業員も辞めていきました。
第2回目の大量離職です。
しかし、この時の気持ちは-8です。
今までのさまざまな負の連鎖、大量離職を体験していたため、気持ちの準備をしていました。
今回の大量離職ではそこまで落ち込むことはありませんでした。
【弟がNOと言っていたことを掘り下げる】
幹部として動いてくれていた弟が退職してしまったのですが、
そう立ち止まっているわけにはいきません。
退職の本当の理由はわかりませんが、
弟と僕との間に、経営に対する考え方の違いはあったと思っています。
前進をしていくために、弟がNOと言っていたことを深堀して、
課題を見つけて解決していこうと前向きな気持ちになりました。
実は2014年は、経営においてさまざまな変化をさせていた時期でもありました。
初めて新卒をとったり、社風改善や価値観育成をしたりと、
まるでインナーマッスルを鍛えるかのように、会社の根幹を変えていきました。
弟は「勉強をするよりも現場やれよ」という現場人間の考えだったので、
そこが弟にとってはやりづらかったのかなと思いました。
しかし、きちんとした組織作りをするためには、このようなことが必要だと思いました。
【2016年幹部NO.3が退職】
弟が辞めた2年後に最後の幹部が辞めました。
4人いた幹部のうち、僕意外の3人が会社から離れていきました。
さすがに、僕が何か原因があるのではないかと、
かなり落ち込みました。この時の感情はー10です。
この時の彼も、きっかけは家庭の事情でした。
家庭でうまくいかないことが起こっている時に、
仕事への不満が募ってしまい、退職へつながってしまったのだと思います。
それが手に取ってわかるかのように、彼を絡めたもめごとも多くなりました。
人を辞めさせたり、人ともめたりすることが起こるようになりました。
その時に、会社のトップの僕が白黒をつけるわけです。
正しいことは正しい、正しくないことは正しくないとはっきりと答えを伝えます。
もちろん、彼の身勝手な行動で始まったもめごとの場合は
「君が悪い」とはっきり告げます。
そうすると
「なぜ味方になってくれない」「なんでかばってくれない」
という感情が芽生え、最終的には退職へつながってしまいました。
彼の場合は、彼を追って辞めていくような大量離職はありませんでした。
【NO.3の代わりをパートに】
当時、幹部のNO.3が担っていたのは、総務の仕事でした。
この総務の穴をどのように埋めるかという事を考えました。
この穴を埋めるために、今いるメンバーでどうにかしないといけません。
人がいなくなった時、
特に大事なポストに穴が開いてしまった時、考え方を変えるチャンスでもありました。
果たしてその場所は、本当に幹部や社員だけがやらなければならないのか。
今までは、絶対に上層部がやらなければならないと思い込んでいましたが、
実際にいなくなったらいなくなったで、その穴を埋める人は、
その業務さえできてしまえばパートでもいいという答えに達しました。
もちろん、業務の中には、その役職に就いた人しかできない仕事もあります。
しかし、今回の総務は誰でもできるような業務でした。
それを、複数人でできるようにしたことにより、穴が埋まっていきました。
【得るは捨つるにあり】
幹部の退職、それに伴う大量離職。
それを体験して、
何かを得るためにはまずは失う(捨てる)ことが必要なのだとしみじみ思いました。
捨てないで「なんでも得よう」としてもうまくはいきません。
コップにたくさんの水が入っている状態で、さらに水を足すことはできません。
少しコップの水を減らしてから、水を入れることができるようになるのです。
そのたびに会社が変わっていくことを体験し、今いる古参のメンバーもそれを見て来ました。
まさに、ピンチになってしまった時は、変わるチャンスなのだと、この年表を見て思いました。
【伝える勇気を持つ】
今までどんな人材でも、クビにするということはしてきませんでした。
縁を断ち切りたくないと思う僕が、最も苦手とするところです。
しかし、そう思っていても、今まで経験から、
「察してほしい」「いつか気づくだろう」という期待を持つことはせずに、
しっかりと伝えることはしていこうと理と気がつきました。
そのためには、まず株式会社セイリョウの枠組みを
しっかりとすることが大切なのではないかと考えています。
それを軸として、
弊社の枠組みに合わない人にはしっかりと教えてあげるということをしていきたいです。
「人は頑張ればなんとかなる」という考えは捨てきれません。
しかし、弊社の枠にはまっていない人にいくら
「がんばれ」と言っても、お互いが疲れてしまいますし、
そこで結果退職を選んでしまったら、頑張った時間も無駄になってしまいます。
もちろん極力は言いたくありません。
しかし、社長の僕がしっかりと伝えることが大切なのだと思っています。
【しっかりと見極めをしていく】
株式会社セイリョウで働いていく人材の線引きはもちろんですが、
今後は役職や役員の見極めもしていきたいと思っています。
今までは長く働いているから、
近くに助けてくれる人が欲しいからという理由で役員を無理やり配置していました。
その人の能力を考えず、
全て会社の都合でその人に任せていたと思っています。
今考えると、人間性や能力を見た時に、
役員になるには力不足だったのではないかと思う人もいました。
その人の能力や結果を見て、頑張らなければいけない段階なのか、
そこまで至らない段階なのか、その見極めをして、必要であれば役員投与もしていく。
そのような仕組み作りや見極めをしていきたいと思っています。
【大人数よりもちょうどいい人数で】
能力の見極めは従業員にも言えることです。
「この人の能力では、正社員よりもパートとしてやっていった方がいいのではないか?」
と思ったら、そのように促したり、
逆に「社員として働けないだろうか?」と評価したりしていきたいと考えています。
ある意味ランク付けのようなものです。
そのようにしていくと、おそらく人は集まりづらくなってしまうと思います。
しかし、現状では大人数で会社を拡大していこうとは考えていません。
ちょうどいい人数で土台をしっかりと作って、
売り上げを伸ばしていきたいと思っています。
売り上げの面でも、
大量離職した時に売り上げが伸びました。
なぜか逆に社風に合わない人がたくさんいた時の方が、
トラブルも多くコストもかかっていました。
また、結局のところ、
大人数になってくると僕との考えの溝もできやすくなってきて、
トラブルも起きやすくなってきたのだと思いました。
【僕が楽しいと思うチームを】
山あり谷ありを経て、
現在も成長途中の株式会社セイリョウですが、
今が一番良い人材バランスになっているなと感じます。
やはり、社長である僕が従業員に気をつかっていて、
僕がやりたいことを我慢している。
さらに従業員の方が
やりたい放題やっているという状況は良いものではありませんでした。
少なからず我が社においては、
会社のことを四六時中考えているのは僕だと思っています。
僕が経営について導き出した答えは、あながち間違いではありませんでした。
だからこそ、僕が楽しくなってくるチームを作ることが大切なのだと考えています。
「みんな僕のために働け」と王様になるつもりはありません。
僕がしたいことに対して、応援してくれる、協力してくれる、
作り上げていってくれるチームが、株式会社セイリョウが良くなっていく秘訣なのだと思います。
2024年を振り返る
見直しの2024年
2024年は本当にいろんなことがありました。
中でも一番の出来事は、
大事にしていた幹部のスタッフが辞めたことです。
仕事の中でも大切な業務を担っていたので、
その後の立て直しをどうするかを考えました。
そこで考えたのが、社内を見直すことでした。
見直したモノは以下になります。
・目に見えるモノのメンテナンス:レイアウト
・目に見えるモノのメンテナンス:買い物・備品補充
・目に見えないモノのメンテナンス:朝礼
・目に見えないモノのメンテナンス:気持ち
・目に見えないモノのメンテナンス:正しい情報
・目に見えないモノのメンテナンス:物事の奥にあるもの
詳しく記していきます。
目に見えるモノのメンテナンス:レイアウト
一番初めに見直したのは社内のレイアウトでした。
それまでは、ちょうどいい機材の量や配置をしていたのですが、
辞めていった幹部のスタッフが、自分勝手なレイアウトに変えていました。
僕はそれを従業員みんなの総意で行ったと思っていたので、
特に何も口出しはしませんでした。
ところが後々聞いてみたら、その人の独断で行っていたそうなのです。
例えば、机が9つあるとして、
そのうちの2つを自分たちの物やプリンターを置くことに使っているという状況でした。
これは経営者としてはすごくもったいなく感じるものです。
せっかくその2つの机があるのであれば、モノを置くのではなく、
人が座って作業をするスペースとして使ってほしいと考えます。
もし、新しいスタッフが2名入ってきた時に、
新たな机とイスを買いそろえなければならなくなります。
余計な経費がかかってしまいます。
そのスペースさえ空けてしまえば、
余計な経費がかかることはないわけです。
その余計な物やプリンターを整理して、
社内のレイアウトを新しくしました。
目に見えるモノのメンテナンス:買い物・備品補充
また、備品の購入も、
会社の中では月に2回と決めていました。
外に出て実店舗で買い物をしたり、
ネット上での購入をしたりとさまざまな買い物のし方はありますが、
月の回数は決まっていました。
しかし、それも2回に収めることがなく、
何かにつけて何度も買い物に出たり、
思いついた時に注文をしたりしていました。
さらに、会社が必要としないものも購入したりしていたようです。
大変非効率で、経費も必要以上に使っていました。
このように決まったルールが壊されて勝手なルールが作られていたなと思いました。
目に見えないモノのメンテナンス:朝礼
目に見えたモノのルールもこのように壊されていたのですが、
目に見えない大切なモノも気がつけば壊されていました。
例えば朝礼。
毎日朝礼は行うというルールを置いていたのですが、
そのスタッフの「今日はやらなくていいんじゃない?」
の一言でやらない日もあったそうです。
もちろん、社長の僕がいない日です。
みんなも、朝礼の大切さはわかっていると思うのですが、
早く業務を始めたい、朝礼は面倒だという考えが多少なりともあり、
その人に賛同してしまっていたんだと思います。
「目に見えていたモノを整理していくと、
目に見えないモノのおかしいところが見えてくるんだな」と思いました。
他にも、社内で決めたやるべき業務を、
自分がやりたくないがために、
やらなくていいように操作をしていた、なんてこともありました。
そのようにして個人の勝手な理由で、
ルールを変えていったため、
他のスタッフが動きたいように動けなくなっていきました。
ちなみに「他のスタッフからの反発はないのか?」と思われるかもしれませんが、
その人は幹部の人なので会社の意図だろうと思って、
みんな言うことを聞いていたそうです。
しかし、会社の意図とは全く別のことを言っていたのです。
このように変なルールと変な習慣ができてしまったことで、
トップが言っていることが、会社内に浸透しない、
実現しないということが起こっていました。
目に見えないモノのメンテナンス:気持ち
現在は定期的に面談をやっていますが、
前は「面談をやろう」とアナウンスをした時も、
「面談やるんですか?!」「メンタルの病院ですよね?!」
と茶化している事もあったようです。
しかし、実はスタッフの中には、
面談をした方がいいと思っていた人もいました。
そのような貴重なスタッフの考えも、大きな声で茶化される事で、
かき消されてしまっていたようです。
今では「面談をぜひやりましょう」という雰囲気になってきて、
実際に面談をすることで、お互いの考えがわかったり、
気がついたりすることも多くなってきました。
目に見えないモノのメンテナンス:正しい情報
メンテナンスを行ううちに、
社内の正しい情報が僕の耳に正しく入ってくるようになりました。
社長として業務の進捗や問題、
社内の雰囲気を常日頃から知っておきたいものです。
しかし、それも辞めていった幹部が、
都合のいいことは僕に流して、都合の悪いことは、
黙っているようにとみんなに口止めをしていたそうなのです。
正確に言うと、「言わない方が良いかも…」という口止めの心理状態になっていた様です。
だから、
僕が電話で業務の確認などをした時に
歯切れの悪い返事が返ってくる事がたびたびありました。
「このスタッフ、なんかおかしい…何かあったか?」と、
不審に思うことはあったのですが、
それ以上詮索することはしませんでした。
後々、みんなに話を聞いていくとそういうことがあったそうです。
その時の社内の空気はどこか圧があり、
怖かったと面談で話すスタッフもいるほど、
社内環境は見えないところで悪くなっていたようです。
現在では、
スタッフ一人ひとりの考えがしっかりと僕の耳に入ってくるようになり
「正しい情報が正しく入ってきているな」と思うようになりました。
それは、僕が望んだ社風のカタチでした。
目に見えないモノのメンテナンス:物事の奥にあるもの
目に見えるモノをメンテナンスし終えると、
目に見えないモノへのメンテナンスに入れるようになりました。
社長の僕と残った課長とで、
さまざまな事の分析をするようになりました。
「これはどうなんだろうね」「これはどうしようね」と、
いままでスルーしてきた“根底にある大切なもの“にも
目を向けられるようになったということです。
それは、突き詰めて考えると、
答えを出し切れないモノもあるかもしれません。
しかし、目を背けず考えられる余裕や時間ができたのではないなと思います。
社長取り扱い説明書・セイリョウ幹部とは
今回のようなことが起こってしまっていた背景に
「長く会社に勤めているから幹部になれる」という
間違った考えがあったからだと思います。
さらに「社長はこういう考えだ」という思いこみで、
都合の悪い事は伏せられていたことも事実です。
このようなことが今後起こらないように、
以下のものを作成しています。
「社長の取り扱い説明書(仮)」「セイリョウ幹部とは(仮)」というツールです。
これは現在の課長が作成しています。
「社長の取り扱い説明書(仮)」は社長の考えや性格をまとめたもの。
「セイリョウ幹部とは(仮)」はどのような人が幹部に着任するものなのか、
幹部の在り方などが明確に見える化されたものです。
こちらは現在まだ製作途中なのですが
「会社を理解する力」「自己理解ができる力」など、
幹部になるために必要な力を書き綴り、
最終的にはPowerPointで社内に発信していきたいと考えています。
このツールを作ることにより、
社長とはどんな考えなのか、どんな性格なのか。
幹部とはどんな人が着任するのがいいのか、
どんな心構えの人がふさわしいのかが目に見えてわかってきます。
2025年の抱負
2024年の失敗は、
会社作りの根幹にかかわってくると考えています。
今まで幹部になってきた人は、僕の近しい人でした。
しかし、その後全員僕から離れていきました。
原因を突き詰めて考えると、
僕が僕自身のことを理解していなくて、
周りの人が僕の性格を勘違いしてしまう状況を作りだしてしまった、
という答えにたどり着きました。
僕は基本的になんでも受け入れてしまう性格です。
誰かが「やりたい」と言ったことは、
基本「やってみよう」という考えになります。
しかし、それを聞きすぎたことによって「
ここからはやってはいけない」というボーダーラインを
ぼやけさせてしまっていたのかもしれないと思いました。
人間、親しくなると、
その役職や立ち位置、ポジションの関係性に甘えが出てしまうものです。
そこで勘違いが始まり「この社長は言う事を何でも聞いてくれる」
という考えになってしまいます。
ただ、どうしても譲れないところが出てくると
「なんで私が言っているのに社長は言う事を聞いてくれないの」と
引っかかりが出てきてしまいます。
そこから会社への不信感が出てきます。
もちろん、それは身勝手な考えです。
近すぎる距離感にもデメリットがありました。
2025年はスタッフと社長の距離感というものを、
改めて明確にしていきたいなと思います。
また、社長業にもっと専念していきたいと考えています。
僕が社長業以外のことをやり過ぎてしまったがゆえに、
距離感のバランスも崩れてしまっていたのだろうと思います。
これが従業員5人程度の会社であれば、
社長も現場に出て会社の利益に繋がる実業務をしないといけないのですが、
従業員が40人、50人と増えていくと、
社長は社長業に専念しないといけないのではないかと
考えるようになりました。
そういう意味で、
2025年は現場に出ることはあまりせず、
社長業に徹したいと考えています。
さらに、これは現在の課長の目標ではありますが、
2024年よりも社内研修に力を入れて、
今までのような「散らかった考え」を整理して、
社内にしっかりと発信していきたいと思います。
2024年最後に起こったターニングポイント
株式会社セイリョウのターニングポイント
2024年12月、
株式会社セイリョウに大きな転機が訪れました。
この出来事は、弊社の根幹を大きく揺るがす出来事でした。
もちろん、今までの弊社の歴史の中では、
ありえない事ですし「そんなことはできない」「失敗する」と
鼻から思っていました。
目まぐるしく上昇する物価。
そのあおりは、
もちろん株式会社セイリョウにも影響を与えました。
どのくらいの影響かというと
「2025年には廃業してしまうかもしれない」と
危機感を持つほどの影響です。
それを打破すべく、
それまでもさまざまなことに取り組んできました。
あらゆる方法を試しました
昨年、
重要な業務を取り仕切っていたスタッフが退職し、
それに続く大量離職。
それを皮切りに、
その業務やレイアウト、
社内コストの見直しを行い、
無駄を徹底的に省きました。
思っていた以上の無駄が発覚し、
少しは会社の存続の足しになるかと
思ったのですが微々たるものでした。
そうでなくとも、
今までも緻密なコスト削減をしてきたつもりです。
しかし、この異常な物価高の前には、
その努力も全く歯が立たちませんでした。
料金の値上げに踏み切る
こうなった時に
他企業であれば『値上げ』の三文字を
実行すると思います。
しかし、運送業はその三文字には
縁のない業種という、
レッテルが貼られています。
社長の小林の頭の中にも、
そのようなイメージが定着していました。
「お客様には負担をかけずに、
何かを削り続けて経営状況を立て直すもの」。
そう思い込んでいました。
そんな切羽詰まっていた2024年11月、
お取り引きの企業のひとつでもある
派遣会社の経営者の方と、
お話をする機会がありました。
その方も「値上げをしないと人が集まらない」と、
かなり悩まれていました。
そのお話を聞き
「もしかすると、弊社も値上げをしないといけないのかもしれない」
「チャンスは今しかないのかもしれない」と
考えが変わり始めました。
実に約30年ぶりの
大幅な値上げに踏み切る決心をした瞬間でした。
約1カ月の準備期間
世間は値上げラッシュの中、
「運送業は別」「値上げはタブー」という
イメージが定着してしまっている状態で、
値上げ交渉をするには生半可な準備では
到底取り合ってもらえないと思っていました。
そこで、今まで緻密に行ってきたコスト削減、
その時に記録してきた社内の利益や経費、
車両ごとの細かなコストなど、
株式会社セイリョウのあらゆる数字の
全てを整理して資料に落とし込みました。
それをお客様にお見せすることによって、
理解してもらえるのではないかと考えました。
会社にとって、内部事情、
特に数値の部分をお客様に見せるという事は、
かなり辛いことですし、
恥ずかしい事でもあります。
しかし、そうでもしないと取り合ってもらえない、
失敗したら2025年には廃業してしまうかもしれない状況に、
背に腹は代えられないと思いました。
そして2024年12月、
弊社とお取り引きをしている
お客様一社一社に、
値上げ交渉を始めていきました。
希望価格は+8000円
普通値上げをする場合、
何か新しいサービスを加えて提示しないと、
お客様にとっては魅力を感じていただけないものです。
今まではそのようにして、
少額の値上げ交渉をしてきました。
しかし、今回は純粋に値上げだけの交渉になります。
そのために用意したのが、
弊社の全てを表した数値の資料でした。
その結果、ほとんどの企業様より、
満額での値上げは難しいものの、
半分以上の金額の値上げを了承していただきました。
実に150万以上利益を出すことができたのです。
「知らなかった」との声も
今回の値上げ交渉の際に、
相手の企業様より上がった感想として、
「こんなに切羽詰まった状況に
なっているとは知らなかった」という声です。
今回、機会を逃さずに、
手の内を見せて、値上げの交渉をしたことで、
弊社の経済状況を知っていただくことができました。
逆に、何もしなかった場合を想像すると
「このように言っていただけるお客様との
関係もなくなっていたのだな」と安堵しました。
成功に導いた他の要因①:綿密なコストカット
今回の大幅な値上げの成功には、
現状の資料と社長の交渉力だけではなく
他にも要因があります。
まずは、長年行ってきた緻密なコストカットです。
これがあったことにより、満額には届かなくとも、
今回のような少しの値上げ額でも利益に繋がりました。
日頃からきっちりとコスト管理をしていなかった場合、
値上げをしても利益には届かなかった可能性があります。
さらに、車両ごとの細かな数値を
資料としてすぐに作成することも難しかったと思います。
全ては事前準備の賜物だったのだと感じています。
成功に導いた他の要因②:さまざまな取り組み
売り上げや利益に直接関係せずとも、
間接的に行ってきた取り組みも、
値上げのチャンスを掴むための
要因だったように感じます。
「HPでの新規お客様の集客」
「市場環境の正しい情報収集力」
「人材育成を行い、気づく力の向上」など、
それらがチャンスを掴み取るための
準備として大きかったのではないでしょうか。
中でも、幹部(課長)が力を入れている
『コーチング』の導入は、
以前のマイナスな思考を、
プラスの思考に変化させてきました。
配送業務ひとつとっても、
以前は新たな配送業務に対して
愚痴やマイナスな言葉が出てばかりでした。
しかし、コーチング面談を取り入れた結果、
「一度やってみる」というスタッフ
の気持ちの変化が垣間見えてきました。
このような変化に、チャンスも集まってきたのだと思いました。
未だにこの『コーチング』を知らない同業他社が多い中、
弊社は早い段階で実行し成功しています。
それも日ごろの努力の賜物だと思います。
成功に導いた他の要因③:5S活動の徹底
5Sと聞くと「整理・整頓・清掃・清潔・躾」
思い浮かべると思いますが、昨年弊社では
「目に見えないモノの5S」も
打ち出し実行してきました。
1,株式会社セイリョウとして求める人材の明確化
2.組織図の整理(個々人で崩していた指示命令、業務の再整備)
3、社内ルールの徹底(マイルールの排除)
4、社内で不要となる人材の明確化
5,価値観の共有方法(愚痴ではなく情報の共有の仕方)
少し厳しい言葉の内容も入っていますが、
このように社内を整えていった結果、
スムーズに値上げへの動きに移ることができました。
また未来の話ですが、
値上げ後のこれからも、
5Sを意識することによって、
より業務に集中し、
お客様の笑顔にも繋げていくことが
できると考えています。
せっかく値上げの了承をいただいたのですから、
お客様にもより満足していただくような
働き方をしないといけません。
そのためには内部を
整え続ける必要があります。
その軸になるのはこの5S活動だと考えています。
『値上げ交渉は皆さんがやるんですよ』
定期的に参加している
「全日本トラック協会」のセミナーで、
講師の方が言っていた言葉です。
その時に参加したのは幹部の課長でした。
その言葉を聞いて課長は「
値上げ交渉していいんだ」と驚いたそうです。
『運送業は値上げをするものではない』、
そんなイメージに囚われて、
頑なに値上げをせず、
経費削減も限界まで行った同業者の中には、
廃業になった会社もいくつかありました。
また「もうやっていけない」と
苦しい胸の内を話す同業者も見て来ました。
今後は『運送業でも値上げ交渉は可能』という
イメージに切り替えが大切になってきます。
いや、今どんどん動き出さないと
手遅れになる可能性があります。
今、値上げ交渉行うことによって、
経営が回復する可能性は大いにあります。
もし、それでも値上げに1円も応じない、
気持ちの賛同を得られないお客様とは、
「もしかすると、もう潮時なのかもしれない」と思い
離れていくのもいいのかもしれません。
廃業の心配から脱却し、始まった2025年
今回、大きな値上げ交渉をした結果、
2025年に懸念していた廃業の危機は免れました。
それは、社長の値上げ交渉がうまくいっただけではなく、
今までの会社の努力がもたらした結果でもあります。
日ごろ現場や社内の業務で、
スタッフ一人ひとりがやってきた努力の積み重ねが、
このターニングポイントを生んだのだと思っています。
これからも株式会社セイリョウは、
さまざまなチャンスを掴み挑んで、成長していきたいと考えています。
退職代行を使う世の中について
退職代行が利用される昨今
4月、世間では新年度を迎え、新入社員を称える入社式が次々と行われる時期です。
社会人としての門出を迎えた彼らは、これから会社のために働いていくわけですが、
そんな中「出社3日目にして退職代行により退職の電話が会社にかかってきた」という話も。
もう毎年恒例の風物詩のように感じます。
とある退職代行の企業は、起業した時にはまるでアパートのような狭い一室を借りて、
3~4人ほどの従業員でやっていたが、今ではしっかりとした法人用ビルのテナントを借りて、
従業員も数十名になったという大成長を遂げた、という話も聞きます。
それほど、退職代行を使うユーザーは増えているという事です。
退職代行の本来の役割とは
従来の退職と言えば、
企業側と労働者側が話し合いをして両者円満な退職に繋げるということが、通常の流れでした。
しかし現在では、退職代行の会社が企業と労働者の間に立ち、
労働者の声となり希望に沿った退職ルートに向かうということも
退職の方法のひとつになってきました。
「このようなサービスを使わずに自分の口から退職を申し出ればいい」と考える人が、
現在では大半かと思いますが、今まで直接退職を申し出てスムーズに、
そして双方の希望通りの退職ルートに向かった方はどのくらいいるのでしょうか?
もちろん、正常に退職された方の方が多いと思います。
しかし、そんな中でも、スムーズに退職できなかった人、
有給消化もさせてくれなかった人、退職直前まで働いていた分の給料が払われなかった人など、
さまざまなトラブルになるケースも少なくなかったと思います。
そのトラブルに対して、
泣き寝入りをするのは労働者の方が多かったのではないでしょうか。
スムーズに退職へ進むことができるように、
労働者の希望に沿った退職の流れになるように、
労働者の間に立つ仕事をするのが退職代行だと思います。
退職代行を使うブラック労働者
正常な退職の流れに繋がるように企業と労働者の間に立つ退職代行。
その案件の中には、ブラック企業ならぬ、ブラック労働者もいるようです。
入社前に伝えられた仕事内容と違った、
入ってみたら社内の雰囲気が暗かったなどの理由なら、まだかわいいものです。
先日読んだ記事の中には、
「会社の備品を壊してしまったので明日退職したい」
「仕事のお客様に明日怒られに行かなければならないので退職したい」など、
「どうしようもない…」とため息が出てしまうほどの理由で
退職代行を活用する人がいるというのを読みました。
これは、さすがに退職代行側も呆れてしまう理由ではないでしょうか?
そんなブラック企業ならぬ、
ブラック労働者も現在増えてしまっているというのも、現状だと思います。
しかし、このブラック労働者も、
人材育成をしっかりすれば生まれない存在なのではないかと考えています。
新入社員の退職を生まないためには
株式会社セイリョウでは、人材育成に以前から力を入れています。
それは新卒や転職による新人スタッフはもちろん、
既存の社員の意識を上げていく人材育成にも取り組んでいます。
新卒が入社し、1カ月ほどでやめてしまった場合、
雇用コストは約100~200万ほどかかります。
その金額を本人がいなくなってから
どのように補填していくかということを考えなければいけなくなります。
ではどのようにすれば、新入社員がすぐに辞めない取り組みができるでしょうか。
それは、新入社員と既存スタッフとの考えのズレをできるだけなくすことだと思います。
そのためにまずできることは、
既存スタッフへの考え方のズレを少しでも減らすことが大切だと思います。
既存スタッフへの意識向上
実は現在、既存スタッフに向けた
「新人スタッフに向けての心構え」という資料を作成しています。
そこには既存のスタッフが感じている、
今まで出会ってきた新卒(若者)の共通点としてあがってくる特徴が記されていて、
それを既存のスタッフへ共有し「ではどのようにして接するのか」と、
接し方へのアドバイスへと繋がっていくように作りました。
株式会社セイリョウはじめ、企業にはさまざまな年齢のスタッフが働いているものです。
その一人ひとりの若いころを思い出しても、
時代によって若者の傾向や共通の考え方、行動の方向性などはまったく違うものです。
40代のスタッフの若いころの話をしても、今の新卒の子にはまったく響きません。
その認識のズレを既存のスタッフ同士で共有して、
新入社員を迎えるにあたっての心構えをしっかりと持っていきたいと考えています。
この仕組みを外国人労働者にも応用
株式会社セイリョウでも、この人材不足を解消するために、
外国人労働者を受け入れなければならないだろうと考えています。
そのために現在、ミャンマーに面接へ行く段取りを立てています。
ミャンマー国内での情勢上、現在では大学を出ても仕事がないため、
日本をはじめ他国へ仕事の活路を見いだすしかないと考えている人がほとんどだそうです。
そのことから、初めて外国人労働者を雇うための、試運転としても最適な国だと思いました。
また、現在考えている「新人スタッフを迎えるための心構え」は、
外国人のスタッフを雇うためにも必要だと思いました。
日本国内でも、現在の新卒と既存のスタッフの新卒時代の考え方は違うため、
さまざまな認識のズレによる残念な理由の離職があります。
外国人であればなおさらです。
文化や言葉、考え方は、日本とは全く違います。
外国の新人スタッフ、
既存のスタッフ両方が仕事上での大きな苦悩に見舞われないために、
より良く業務に励んでもらうためにも、この心構えは既存スタッフ側にも必要だと思っています。
ブラック労働者を生まない人材育成
新人育成、人材育成に力を入れ始めてから、
今日まで人材に関する全てがうまくいってきたわけではありません。
それを懸命に行っていても、古参スタッフの退職、
それに伴う大量離職がありました。
仕事上での人の心を育てるわけですから、
ひとつのマニュアルで全てがうまくいくわけではありません。
そんな中でも、同期の仲間が大量離職と共に退職をしていったとしても、
弊社に残った元新人スタッフがいます。
彼は社会人としての成長が緩やかで、社長の面談がすこぶる多かった社員です。
失敗をした後に“叱られて、振り返り、反省をする”ということをとにかく繰り返してきました。
この繰り返しはマニュアルの中に組み込まれています。
もしこの仕組みをしっかりと確立しなかった場合、
彼はただ「社会人として失格」だの「仕事ができない人間」だのと、
くくられて見捨てられる存在だったのではないでしょうか?
しかしマニュアルを繰り返し行い、既存のスタッフもそれに沿って指導をしていった結果、
気持ちや感情の面でも前向きな傾向になり
「まずやってみよう」という考えになるようになりました。
そして、やってみた結果の情報共有を大切にできるスタッフに成長しました。
これはただの精神論で育て上げたわけではなく、
そのマニュアルに沿ってやっていった結果なのだと思いました。
ブラック労働者が生れないために大切なことは、
この人材育成の確立が必要不可欠なのではないかと思っています。
これからも、株式会社セイリョウからブラック労働者を生まず、
労働者と会社側がより良く業務に励めるための環境を作っていきたいと考えています。
外国人労働者雇用
セイリョウ、外国人労働者に四苦八苦
ついに、外国人労働者を雇う決意
以前から人材育成に力を入れてきた弊社。
それは、新卒や転職の新人スタッフ全員を対象に行ってきたことでした。
しかし、それにも関わらず、この物価高とさらには若者の価値観の変化で、
新たに入社してもなかなか会社に人材が定着しなくなってきました。
新卒も入社約1カ月でやめてしまうということが起こり続けています。
新入社員1人を雇うまでにかかる採用コストは約100~200万円。
それを、本人がいなくなった後、会社が頑張って取り戻してくのです。
新入社員が辞めない仕組みを作る、良い会社に成長していく、
ということは何年も行ってきましたが、ここで更なる別の対策を講じることにしました。
それは「外国人労働者を雇う」ということです。
ここ10年で増加した外国人労働者の数
厚生労働省が発表した外国人労働者の登録人数は、
令和6年10月時点で約230万人。
大変多くの外国人が日本で働いています。
それゆえ大小問わず日本企業が外国人を雇用することは当たり前になってきました。
昨今では日本人より外国人労働者を雇うメリットが大きいという風潮もあります。
日本人を雇おうとすると、採用コストに100~200万円かかってしまうことに対して、
外国人労働者の方がよりコストが少なく見積もることができます。
また、他企業の実体験や実際に肌で感じた印象として、
外国人労働者の仕事の覚えや身につく早さが、日本人よりも早いのではないかと感じました。
自国から離れ他国で働くための緊張感が備わっているのだなと思いました。
外国人を受け入れるにあたり、中には眉を顰める人もいますが、
それもこれから関わっていく環境に比例していくのではないでしょうか。
こちらもちゃんと受け入れる環境を整えたうえで迎え入れて接していけば、
大きな問題は起こらないように感じます。
在日の外国人労働者を雇用
実は今年になって、2名の外国人との面接を行いました。
2人とも入社までこぎつけました。
1人目はミャンマー国籍で日本永住権を持ち、
15年ほど国内にいる男性。当時は日本人と一緒に面接をして、
外国人に向けた性格分析テストなども受けてもらい、入社に至ったのですが、
2日目くらいに出勤しなくなってしまいました。
その後、弊社に電話をかけてきて、他の会社と天秤にかけていたことがわかりました。
さすがにそのような人を置いておけないと思い、こちらから入社を断りました。
2人目は、イスラム圏で配送業経験者、Wワークで受けに来た人でした。
無事入社が決定して、研修期間も終わり「さあ本格的に働いてもらおう」
と思った矢先に時給交渉をされてしまいました。
もちろん、求人募集要項に時給の掲示はしてあります。
それを納得したうえで、弊社へ足を運んだのだと思っていました。
結果、提示してある時給では納得されず退職となってしまいました。
日本人雇用の時には起こりえなかったトラブルに、小林社長も驚くばかりでした。
しかし、その2名の出来事により「外国人を雇うということは…」という心構えができました。
もちろん、今後これ以上の何かが起こる可能性はありますが、良い勉強になったと思っています。
セイリョウ、海外へ面接の準備をする
外国人ならではの良さ
先だって国内にいる外国人労働者の対応をして、
結果としては、こちらが損をする内容になってしまったのですが、
日本人にはない価値観を垣間見ることができたと感じました。
2人の外国人と対話をしてみて、
ふたりとも「自分の主張をはっきりと言うということに抵抗を感じない」のだなと思いました。
日本人は嘘でも「はい」と言ってしまうところも、
2人はちゃんと自分の希望を伝えてきました。
さらには、自ら社長相手に臆することなく交渉をする姿勢も見せました。
これは日本人にはない考えや価値観だと思います。
さらには覚える速度も速いとなれば、
外国人労働者には優秀な人が多いのではないかと考えます。
また日本人よりも採用コストが低いこともなれば、
日本人で労働者を募るよりも、
総合的に考えればメリットが多いという気がしました。
ミャンマーでの現地面接
早速、2025年6月初旬にミャンマーでの現地面接を計画しています。
なぜ、ミャンマーを選んだかという事にも理由があります。
現在ミャンマーから日本に雇用目的で来る労働者が
増えているという話を聞きました。
ミャンマー国内では良い大学を出ても、
仕事に就けない現状が国民を悩ませているそうです。
そんな話を聞き、手始めの現地面接としてもやりやすいのではないか、
人材を見つけやすいのではないかと考えました。
入社が決定した後、すぐにトラックを運転するわけではありません。
入社が決定した後に長い期間研修や実習、テストなどを行って、
実際に日本で働いてもらうのは2026年春ごろです。
スムーズに進む準備
実は、現地面接の段取りはスムーズに準備ができました。
その理由には、奇跡的な出会いがあったからです。
とある企業の社長をしている知り合いが、
海外派遣のコーディネートをしていたため、
今回の段取りを全て行っていただけました。
その方は元々飲食店をしていて、
ベトナムの労働者を雇っていました。
新しいビジネスをするにあたり、今回のような海外の人材と日本を繋げる仕事にフォーカスした業種に目をつけ会社を立ち上げたのです。これは渡りに船だと思い、今回のことをお願いさせていただきました。結果、飛行機や現地コーディネート、通訳、ホテルなどの細かな心配をせずに順調に準備が進みました。
こちらで用意したのは、エゴグラムとバイタルチェックの資料です。この程度の準備だけで済んだのは、奇跡的な出会いがあり、それをチャンスと思い動き出したことにあると思います。
迎えるための準備
2025年6月に面接をして、実際に一緒に働き始めるのは来年の春。
それまで社内全員で準備するのは「外国人労働者と働く心構え」です。
外国人を雇うわけですから、今までの日本人の新人の時とはわけが違います。
ましてや、その日本人の新人相手でさえも、受け入れる姿勢が足りなかったと思っています。
相手が外国人となればなおさら気をつけなければならないことが多々あります。
それは特別扱いしろという事ではなく、文化や価値観、言葉などの違いを受け入れながら、
お互いも気持ちよく働き続けることができる環境を作る努力をしなければならないということです。
来年の春に、入社したミャンマーからの労働者が安心して働き始められるように、
その仕組みや心構えを既存スタッフに教育をしていくという準備が必要になっていくと考えています。
セイリョウ、海外へ面接の準備をする
外国人ならではの良さ
先だって国内にいる外国人労働者の対応をして、
結果としては、こちらが損をする内容になってしまったのですが、
日本人にはない価値観を垣間見ることができたと感じました。
2人の外国人と対話をしてみて、
ふたりとも「自分の主張をはっきりと言うということに抵抗を感じない」
のだなと思いました。
日本人は嘘でも「はい」と言ってしまうところも、
2人はちゃんと自分の希望を伝えてきました。
さらには、自ら社長相手に臆することなく交渉をする姿勢も見せました。
これは日本人にはない考えや価値観だと思います。
さらには覚える速度も速いとなれば、
外国人労働者には優秀な人が多いのではないかと考えます。
また日本人よりも採用コストが低いこともなれば、
日本人で労働者を募るよりも
、総合的に考えればメリットが多いという気がしました。
ミャンマーでの現地面接
早速、2025年6月初旬にミャンマーでの現地面接を計画しています。
なぜ、ミャンマーを選んだかという事にも理由があります。
現在ミャンマーから日本に雇用目的で来る労働者が増えているという話を聞きました。
ミャンマー国内では良い大学を出ても、仕事に就けない現状が国民を悩ませているそうです。
そんな話を聞き、手始めの現地面接としてもやりやすいのではないか、
人材を見つけやすいのではないかと考えました。
入社が決定した後、すぐにトラックを運転するわけではありません。
入社が決定した後に長い期間研修や実習、テストなどを行って、
実際に日本で働いてもらうのは2026年春ごろです。
スムーズに進む準備
実は、現地面接の段取りはスムーズに準備ができました。
その理由には、奇跡的な出会いがあったからです。
とある企業の社長をしている知り合いが、
海外派遣のコーディネートをしていたため、
今回の段取りを全て行っていただけました。
その方は元々飲食店をしていて、ベトナムの労働者を雇っていました。
新しいビジネスをするにあたり、
今回のような海外の人材と日本を繋げる仕事にフォーカスした業種に
目をつけ会社を立ち上げたのです。
これは渡りに船だと思い、
今回のことをお願いさせていただきました。
結果、飛行機や現地コーディネート、通訳、
ホテルなどの細かな心配をせずに順調に準備が進みました。
こちらで用意したのは、エゴグラムとバイタルチェックの資料です。
この程度の準備だけで済んだのは、奇跡的な出会いがあり、
それをチャンスと思い動き出したことにあると思います。
迎えるための準備
2025年6月に面接をして、
実際に一緒に働き始めるのは来年の春。
それまで社内全員で準備するのは「外国人労働者と働く心構え」です。
外国人を雇うわけですから、
今までの日本人の新人の時とはわけが違います。
ましてや、その日本人の新人相手でさえも、受け入れる姿勢が足りなかったと思っています。
相手が外国人となればなおさら気をつけなければならないことが多々あります。
それは特別扱いしろという事ではなく、文化や価値観、言葉などの違いを受け入れながら、
お互いも気持ちよく働き続けることができる環境を作る努力をしなければならないということです。
来年の春に、入社したミャンマーからの労働者が安心して働き始められるように、
その仕組みや心構えを既存スタッフに教育をしていくという準備が必要になっていくと考えています。
ミャンマーの現地面接記①
はじめに
2025年6月上旬、人材不足の現状を打破するために、
株式会社セイリョウで働いてくれる人材を見つけにミャンマーへ足を運びました。
現地では人材斡旋会社のアテンドがあったため、心配ごとはありませんでしたが、
実はミャンマーは警戒レベル2になっていたことを知りました。
場所によってはかなり危険な地域もありました。
そんな国の中で行われた今回の面接で、ミャンマーの方々にはかなりの好印象を受けました。
わざわざ現地に出向いて人材を探した甲斐があったと思っています。
ミャンマーという国
日本からシンガポールを経由し、ミャンマーへ入国。
警戒レベルのことを考えると、もっと荒れているのかと思いきや、
降り立った都市ヤンコンはそこまで変な印象は受けませんでした。
ミャンマーは主に仏教の国です。
さまざまな仏閣があり、その中の装飾や仏像には、まぶしいほどの金が施されていました。
近年、ミャンマーの経済は破綻し、平和な地域でも日本のような安心感はありません。
そんな国にこんなにも金を施された装飾や仏像があれば盗まれたり、
金がはがされたりする可能性もあるはずです。
しかし、その仏具が撤去等されず、
ずっとそこに鎮座し続けているということがわかります。
ということは、ミャンマーの人々の中に、仏教の大切な教えが刷り込まれ、
熱心にそれら守り続けられているのだなと思いました。
その信心深さにどこか日本ぽさを感じました。
ミャンマーは旧ビルマ時代、第二次世界大戦中に、日本と戦場となり、
その後も日本軍の占領下で影響を受けてきました。
その時の日本兵の墓はヤンゴンにあり、
ミャンマーの人々が丁寧に管理しています。
どこか日本人と面影が似ているミャンマーの人々には、
とても親近感がわきました。さらにその感情は、
面接で出会った労働希望者の姿勢を見て一層強くなるのでした。
押さえつけられているミャンマー
現地での滞在環境を整えるために、換金やインターネット環境の確認をしました。
すると、ミャンマーでは国際ローニングができないことを知りました。
ではどのようにインターネットをするかというと、
国が指定したシムカードを使う、
または、VPNというアプリを使うという方法でした。
特定の回線からのみインターネットができるという状態です。
そして全てのサイトにアクセスできるわけではなく、
閲覧できるサイトは制限されている状態でした。
まるでどこか政府によって抑え込まれているような感覚を覚えました。
またそれはミャンマー国内の労働関係にも共通して言えることでした。
良い大学に入学しても働く場所がない。
それを国は何も対策してくれず、ミャンマーの人々は我慢しながら生きているそうです。
そんな抑うつとされた状況下だからこそ、
外で働きたいと意欲を示している印象を面接から受けました。
我慢強いミャンマーの人々
働くところがなく、国内情勢も負の状態にあるミャンマー。
そんな中でも人々は我慢しながら懸命に生きてきました。
それはミャンマー国内の環境を見たり面接をして話を聞いたりしてわかってきました。
2021年のクーデターから4年がたった今も、
情勢の回復が見られないため、物価は日本の3分の1と言われています。
もしミャンマーを出て日本で働き、
その賃金をそのままミャンマーの家族に送った場合、
その家族は約3カ月間暮らせる金額になるそうです。
決して現在の日本も裕福な国とは言えません。
しかし、そのくらいの物価の差があれば、
ミャンマー国内から出て日本で働きたいという気持ちになるのも無理はありません。
ミャンマーの現地面接記②
希望を感じた面接
面接を行ったのはヤンゴンの雑居ビル。
日本でいうハローワークを併設したようなオフィスでした。
そこでは、日本で働きたい人が日本語や日本の文化、
日本ではどのような人材を求めているのかなどを学ぶそうです。
そこに集まった6名のミャンマー人。
どんな人がいるのかなと思いながら話を進めていくと、
思いもよらない反応が返ってきました。
それはまるで高度経済成長時の日本のようでした。
自分の夢を語り、日本でやりたいことを語り、自分の好きなことを語り…、
ポジティブな考えや想いが飛び交う、とても楽しい時間でした。
どの人も受け答えがしっかりしていて、やる気に満ち溢れていたのです。
事前に用意していた質問は
「日本語はどのくらい話せるか」「どのくらいの時間働きたいか」など、
あくまで形式的な内容を考えていました。
しかし、一番初めの人と話をしているうちに、
彼らの人となりをもっと知りたくなりました。
「どうして日本を選んだのか」「お金の使い方」
「将来の夢」「どうしてうちを選んだのか」など、
聞きたいことはどんどん増えていきました。
どの質問にも、気の抜けた答えは返ってこず
、どれもその人の芯を感じる答えが返ってきました。
現代の日本人の若者との違い
このようにやる気に満ちた応答がかえってくる
ミャンマー人の若者を見て、
現代の日本人の若者と比べずにはいられませんでした。
株式会社セイリョウに入ってくる近年の新卒では、
どのくらい休みをもらえるか、賃金がそれと妥当かなど、
自分がいかに損をしないで楽をして稼げるか
という気持ちが見え隠れする質問ばかりが飛んできます。
さらには入ってもすぐに辞めてしまう始末。
もちろんそれも働くためには大切なことです。
しかし、こんなにも夢とやる気に満ちたミャンマーの若者の話を聞くと、
これからはミャンマーで人材を探す事をデフォルトにしようかと考えてしまうほどでした。
いや、もう毎年ミャンマーに人材を探しにこようと決心しました。
本当は全員を採用したいほど
面接を行う前までは、
ミャンマーでの人材は1人にしようと思っていました。
しかし、面接を見た後は「全員を採用したい」と思ってしまうほど、
彼らの熱意に感動しました。
しかし、いきなり6人を採用するほどの余裕は、
現在の株式会社セイリョウにはありません。
なので、今回は2人を採用決定として、
補欠として1人(何らかの理由で先2人の辞退があった場合)を選びました。
決定した1人からは、10年ほど日本で働き、
経営のノウハウを身に付けたら、
国に戻って同じ職種の会社をたちあげたいと展望を語ってくれました。
今の日本の若者の中に、
このような夢を語ってくれる人はどのくらいいるでしょうか?
こんな話を聞いたら雇わずにはいられない人材だと思いました。
もちろん面接をした6人全員が、
この規模の夢を持っているわけではありません。
しかし、どの人からも前向きでやる気と覚悟に満ちた返答ばかりでした。
最後に:飛行機の中で
ミャンマーでの現地面接は大成功に終わりました。
後は、来年の春(可能であればもっと早く)までに、
彼らが技能実習生として飛躍し、来日するのを待つだけです。
社長の小林が帰路に就く際に、飛行機の中で考えていたことは
「これからは毎年ミャンマーに人材を探しにこよう」
「その段取りを組んでいかなければ」ということです。
元はと言えば海外に目を向けた理由として人材不足で、
特に若年層が運送業に興味を持たなくなったことにあります。
入ってもすぐ辞めることがほとんどですし、そもそも採用申込がありません。
もう、日本国内での採用には期待せず、
ミャンマーの人材に重きを置いていこうという考えになりました。
本当にこれからの人材採用は、海外に目を向けていくことで、
この人材不足は解消していくのではないかと思います。
来年彼らと一緒に働くことを楽しみにしています。