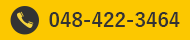会社概要目次
◆代表者メッセージ
◆SDGs達成に向けた取り組み
・環境問題
・健康な働き方
・これからのセイリョウ
・株式会社セイリョウとSDGs①
・株式会社セイリョウとSDGs②
・とだSDGsパートナー紹介動画
◆会社情報
◆会社沿革
◆本社・営業所について
◆デジタコ搭載
◆車両紹介
・軽の冷蔵・冷凍トラック
・冷蔵・冷凍トラック
◆荷物の積み方
・バラ積みバラ卸し
・カゴ積みカゴ卸し(長台車)
・重量物の積卸し
◆無駄な待機時間の見直しで生産性アップに
◆庸車・協力会社様の募集
◆国土交通省主催「企業交流会」に参加
◆人材確保・育成のセミナーで登壇しました
代表者メッセージ
1971年創業以来運送という仕事を通してお客様にサービスを提供してきました。
今まで行ってきた配送業のノウハウを活かし、
介護分野においてもセイリョウが世の中のためにできることはないかと考えました。
介護用品、福祉用具の配送を行っていた実績をもとに介護用品、福祉用具の販売・レンタル事業を開始しました。
個人の住宅から、介護施設への営業も行うようになり少子高齢化の時代背景も寄与し売上も少しずつ伸びてきました。
介護事業を進める中で、介護用品や福祉用具だけではなく、お客様ご自身をお運びすることは出来ないかということを思いつきました。介護タクシー、福祉タクシー事業をスタートさせました。
原点回帰ではないですが、これらの貴重な経験を活かし運送事業の部分での新たな専門サービスとして、冷蔵・冷凍運送事業の強化をはかることとなりました。
特に介護食品、病院食品、スイーツ、アイスクリーム、ジェラートなどの冷蔵・冷凍での配送が必要なお客様の冷蔵・冷凍運送のお仕事のお手伝いができればと考えております。
現在、これからの少子高齢化に対応した運送業づくりを目指していくことで、さらに新しいサービスを生み出す事ができると考えています。
少子高齢化に対応した運送業づくりというのは、
 先ほども言った介護事業で取り扱う、少子高齢化に対応した商品を運んでいく事。
先ほども言った介護事業で取り扱う、少子高齢化に対応した商品を運んでいく事。
運送で培ってきたノウハウを使って、少子高齢化で利用できるアイテムをお客様に届けていきたいと思っています。
そして、現場で働く人材は60代以上を中心に考えています。
60代以上でまだまだ働けるのに引退した方のお話をよく聞きます。
そんな方々に働く楽しさをもう一度セイリョウで経験してもらい、やりがいや生きがいを感じながら、元気を継続して頂きたいと思っています。
もちろん若い世代の従業員さんにも沢山集まってほしいと思っています。
若い皆さんには現場の配送はもちろんですが、パソコンやタブレットが当たり前にある世代だと思うので、ホームページやシステム管理などに積極的に触れてもらいたいと思っています。
その他にも60代以上のパートさんの管理や会社の宣伝など、パソコンやウェブを使う得意なことを伸ばしてもらいながら、共に成長していきたいと思っています。
夢を持って仲間、お客様、会社が笑顔になる為に、協力する気持ちと自立した責任感を持っもらうことで、思いを込めて荷物を送るという姿勢が、安心・安全・真心の「想いやり」の社風を作っています。
そのことが企業文化、社風の根幹価値になり、企業としての存在意義、仲間に求める行動指針の基礎となっています。
セイリョウで掲げている「理念」を全員で共有していくことで、企業や人材の変化に対応し続けることが可能になると考えています。
SDGs達成に向けた取り組み
セイリョウの取り組み
持続可能な開発目標としてSDGsの取り組みが世界中で注目されています。
セイリョウでも現在行っている事やこれから未来に向けて考えている活動内容を紹介したいと思います。
環境問題
弊社は運送業をメインで業務を行っているため、トラックや車の使用は必ず必要となってきます。
そこで問題となってくるのが温暖化の原因とされるCO2排出の問題です。
トラックを使用している以上、CO2の排出は避けられません。
しかし、「配送業だからしょうがない」と諦めてしまっていては、問題解決に動くことが出来ません。
セイリョウでは、どの様にしたらCO2の排出量を少しでも減らすことが出来るかを考え取り組んでいます。
今では一般の車でも当たり前になっていますが、アイドリングのストップです。
配送業の場合は問屋さんの倉庫が混んでいると、待機をしなければならなくなります。
時間にすると1時間や長い時で3時間もの間待機をしなければならない場合があります。
その間にアイドリングをストップしていく事で、無駄なCO2の排出は無くなります。
「自分だけいいや」が環境破壊につながっていきます。
今ではほとんどの配送業者がアイドリングストップを守っていますが、
「自分だけいいや」にならない様に意識を持って配送業を行っています。
また、配送業界では荷物の量や問屋の状況、時期などによって配送にかかる時間が読めない場合があります。
場合によっては一日の配送時間が12時間を超える配送もある様です。
その場合、12時間ほぼずっとCO2を排出し続けている事になります。
そこでセイリョウで行っている対策としては、一日の配送時間を8時間までに制限をかけることです。
常に8時間を超えしまう業務の場合は、取引先に交渉させて頂いております。
この働きかけを行う事で、現在セイリョウで請け負っている配送はほぼ8時間以内に終わる業務になっています。
それまでは時間が読めない配送が多かったので、無駄にCO2が排出されていました。
CO2の排出をなくす事はできませんが、終わりの時間を明確に決めて無駄にトラックを動かす時間を減らすことで、
2~3時間CO2を排出しなくて済む事になります。
この必要以上に動かしていた2~3時間をセイリョウが所有しているのトラック台数約40台分で考えると、
80~120時間無駄なCO2排出を止める事ができているという事になります。
この様に、無駄な時間を少しでも減らしていきCO2の排出を減らす努力をする事で、
配送業でも環境問題に取り組むことが可能と考えています。
健康な働き方
弊社では、60代以上の中途雇用を行っております。
長年働いてきた会社を定年退職された皆さんにフォーカスして、
第二の働きがいや生きがいをセイリョウで見つけて頂きたいと思い60代以上の中途雇用の動きを進めています。
60代以上の雇用を何年も進めていく上で気づいたことは、
60代を過ぎた皆さんでもまだまだ元気でやる気に満ち溢れている方が多いという所です。
このエネルギーをセイリョウでもプラスに活用できるのではないか?と思いこちらの雇用を行っています。
60代以上の皆さんがセイリョウへ来て何がプラスになるかを考えた時に、
《健康的に働くことができる》という点が一番重要な要素だと思っています。
これはSDGsの中の【3,全ての人に健康と福祉を】に当てはまる内容だと感じています。![]()
例えば、出勤時間は朝の4:00~5:00の間なので毎日早起きができ、
健康的な一日のスタートを切る事ができます。
働き方で言えば、セイリョウでは20kg以上ある荷物が続く場合は、
荷主さんに大きなカゴ台車にまとめて頂く様にお伝えしています。
その為、少しの力で荷物を運ぶ事ができ適度な運動をしているのと同じ効果が事が得られます。
もちろん個人の意見も尊重し業務を行って頂いています。
やはり家にいて動かなくなると、気持ちもマイナスに入りやすくなり生き生きとした生活ができなくなってしまします。
セイリョウで働いている60代以上のパートさんは非常に健康的で、前向きな方ばかりです。
更にそんな皆さんの健康を更に維持して頂く為に、
セイリョウでは年に2回の健康診断ができる様に環境を整えています。
実際に健康になる事で前向きな気持ちになっていき、趣味も楽しく取り組んでいる方が多く居ます。
ゴルフや釣り、旅行など様々な趣味で楽しんでいます。
この理解を社内全体で共有していく事で、60代以上の皆さんにも光が当てられ社会貢献に繋がっていく働き方だと感じております。
これからのセイリョウ
SDGsの動きが世界中で活発になっていく中で、我々が行っている配送業も未来に向けて真剣に考えていかなければなりません。
現在セイリョウでは約35台のトラック・ハイエース・軽トラックで配送を行っていきます。

ディーゼル車・ガソリン車で配送を行っているので、CO2の排出量を限りなくゼロに近づけるのは厳しいのが現状です。
そこでこれからのセイリョウでは、ディーゼル車ではなくEVトラックの実用化を目指したいと思っています。
EVトラックとは、電気自動車(EV)のひとつで、電動モーターを原動機とする貨物車両のことを言います。
EVトラックを実用的に活用する事ができれば、
国際的に広がる排出ガス規制もクリーンにすることができ、CO2排出防止だけではなく夜間や早朝の配送などでの騒音削減が可能となります。
2022年現在、各車メーカーでEVトラックの生産が進んでいます。
昔のイメージでは電気自動車は長距離向けではない、値段が高いなど少し手を伸ばしづらいイメージがありました。
しかし、本格的に車メーカーが動き出し他の企業でも活用するようになれば、
今よりも実用的な価格や使いやすさが考えられ、それらの問題は解消されていくはずです。
現在のCO2排出の問題も考えつつ、未来の配送の有り方・EVトラックの活用を視野に入れて、
新しい配送の形を想像していきたいと思っています。
【株式会社セイリョウとSDGs①】
2024年「とだSDGsパートナー」に認定
企業のSDGsへの取り組みが当たり前になってきた昨今、
株式会社セイリョウももちろんSDGsに目を向けて取り組んでいます。
本社を構える埼玉県戸田市はSDGsの普及と啓発に大いに取り組み、
2022年に「SDGs未来都市」のひとつに選ばれました。
その戸田市の取り組みのひとつに
「とだSDGsパートナー」というものがあります。
SDGsの取り組みを行う市内事業者を、
外部へPR支援していくという制度です。
そのパートナーの一企業になるには、
SDGsにしっかりと取り組みをしているか、市の認定が必要になります。
今年、株式会社セイリョウもとだSDGsパートナーへの申請を行い、
5月に認定をいただきました。
株式会社セイリョウのSDGsへの取り組み

「とだSDGsパートナー」で認定を受けた目標は4つです。
目標④質の高い教育をみんなに
目標⑧働きがいも経済成長も
目標⑨産業と技術革新の基盤をつくろう
目標⑰パートナーシップで目標を達成しよう
どれも、従来の想像する運送会社には少し関係性が薄い項目のように感じますが、
今までの弊社の取り組みを思い出したり、
視野を広げて考えたりすれば、大いに合致することがあります。
目標④質の高い教育をみんなに
これは社内研修、社外研修を行うことにより、
社内の従業員全員に同等の教育を受けさせることに成功しています。
さらに弊社では、マニュアルを動画に落とし込んでいるため、
わからない操作方法ややらなければならない作業の順番など、
万が一忘れてしまった場合でも、
それを個々が動画マニュアルを見ればわかる状態になっています。
ある特定の従業員がずっとわからない状態にはなりません。
また、社内外の研修は人材育成にも繋がります。
目標達成や反省、面談などを日々の業務の中に取り入れ、人材育成につなげています。
目標⑧働きがいも経済成長も
弊社では60歳以上の高齢者が働ける職場作りをしています。
「60歳以上でドライバーなんて大丈夫なの?」と思われるかもしれませんが、
株式会社セイリョウで働く高齢のスタッフは
普段から運動やそれに準ずるような活動をしている方が多いです。
若いスタッフよりも若さを感じます。
現在日本は少子高齢化の時代です。
若い人材が不足になっている昨今、
目を向けるのは高齢者だと思います。
なにも、高齢者が1人で若い人と同じ働きをしなければならないわけではありません。
高齢者でも働けるくらいの時間割や業務のシステムを作ってしまえばいいというわけです。
若いスタッフが1人でやる仕事を、高齢スタッフは2人でこなす、
時間を分担して行うなど、やり方はさまざまです。
そうすることによって、働く高齢者スタッフは生きがいを感じ、
さらに会社にとっても利益をもたらしてくれます。
この高齢者の問題に目を向けた取り組みをすることで、
今回認定には至っていませんが「目標③すべての人に健康と福祉を」
にも繋がる部分が出てきます。
株式会社セイリョウは高齢化問題にはこれからも深くかかわっていきたいと考えています。
株式会社セイリョウとSDGs②
目標⑨産業と技術革新の基盤をつくろう
株式会社セイリョウで使うトラックは約20年選手のものがほとんどです。

しかし、その1台1台が100万円の売り上げを出しています。
どれも新品での購入ではなく、中古での購入でした。
中古のトラックだと燃費や耐久性などが心配されますが、
新品とあまり変わりません。
また修理代もそこまでかかりません。
弊社では毎日、使う前にトラックの点検を行いますし、

定期的に点検や清掃も行っています。
そうすることで中古購入したトラックでも十分長く使えますし、
しっかりと利益を出し続けることができます。
これは決して「我慢する」ということではなりません。
「大事にする」ということです。
お金をかけるところ、
かけないところへの考えをしっかりとすることで、
会社にとっての良いお金の使い方、
お金への良い考え方ができてくるのです。
目標⑰パートナーシップで目標を達成しよう
株式会社セイリョウでは、
運送会社ではあまりなじみのない人材育成に力を入れています。
運送業と言えば「トラックのうんちゃん」というのが、
古くからあるイメージです。
人材育成などの研修はなく、
常に何かを運んでいるというイメージがあるのではないでしょうか?
弊社では、さまざまな経験を経て、
人材育成がいかに大切かということを身をもって知り、
今日にいたるまでその取り組みに時間を費やしてきました。
実はそのノウハウを海外の企業や
海外の運送企業に提供できないかと考えています。
もちろん日本と海外では文化が違います。
日本の一企業のノウハウが、
どこまで海外で通じるかはわかりません。
しかし「メイド・イン・ジャパン」は古くから
「売れる」と考えられていますし、
「気づかい」「心配り」「もったいないの精神」など、
海外ではなかなか成しえない日本ならではの内容を入れることによって、
魅力的に感じてもらえるのではないかと考えています。
また、人材育成のノウハウに限らず、
現在デジタルコンテンツへの発信にも力を入れており、
それをまとめてパッケージ化できないかと考えています。
株式会社セイリョウでは動画や成功事例、
HP作成、SNSなどさまざまなデジタルコンテンツを使って発信しています。
その実録をまとめてパッケージ化し
「デジタルコンテンツを発信したいがどうしたらいいか…」と
悩んでいる企業に提供したいと思っています。
さらにさまざまなデジタル媒体を積極的に発信するためには、
そこの専門の方の力が必要となります。
株式会社セイリョウでは
動画クリエイターやライターなどは外部へ委託しています。
社内で無理に頑張ろうとすれば、情報発信を続けることができません。
弊社が積極的に発信できているのは、
外部へ委託しているおかげだと思います。
そのデジタル媒体発信に苦悩されている企業があれば、
現在弊社とやり取りをしている外部の専門家の方を紹介する、
橋渡し役にもなれないだろうかとも考えております。
このようにして、
パートナーシップをさまざまな企業や海外と組んでいき、
SDGsの目標を達成していきたいと考えています。
SDGsの共通項目
認定された4つの目標を深く紐解くと、
共通した言葉が出てきます。
それは「人材育成」です。
目標⑨であっても
「もったいない」「不要なものにお金をかけない」という考えも
人材育成が入っていると思います。
一般に会社のお金を好き勝手使うことは許されることではありません。
しかし「そうしなければならない」と根拠のない理由により、
会社の経費を好きに使おうとする人も中にはいます。
そういう人にもしっかりと考えを共有するために、
人材育成が必要となってきます。
さまざまな人を見てきて身に染みてわかったことは、
人間としての質がしっかりしないと、どんなに良い物を与えても、
どんなに良い事を教えても、生かすことができないということです。
これがSDGsにも連動しているのではないのでしょうか。
株式会社セイリョウはこれからもSDGsへ取り組み、
社会へのより良い貢献ができるように精進していきます。
とだSDGsパートナー紹介動画
会社情報
| 会社名 | 株式会社セイリョウ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 小林 隆文 |
| 住所 | 本社:埼玉県戸田市新曽2263-6 戸田営業所:埼玉県戸田市笹目5-13-5 千葉営業所:千葉県市川市原木2-1701 |
| TEL | 048-422-3464 |
| FAX | 048-422-3445 |
| info@seiryou-senders.com | |
| URL | http://www.seiryou-senders.com |
| 事業目的 | ・運送事業 家具(オフィス・家庭)、精密機器、食品、引越、貨物全般 ・介護事業(福祉用具、介護タクシー、食品デリバリー、施設入居者引越) ・支援事業(物流コンサルティング 業務請負) |
| 資本金 | 1000万円 |
| 設立年月日 | 創業1971年1月26日(設立2001年7月1日) |
| 従業員 | 42人(パートナースタッフ含む)2023年2月現在 |
| 車両台数 | 36台 2023年2月現在 |
| 取引先 | 株式会社 JR東日本リテールネット、株式会社東京凮月堂、埼玉県戸田市立図書館、第一物流 株式会社、アルノー・ラエール、シンチェリータ、フォルトゥーナ、リンツジャパンン(敬称略・順不同) |
| 取引業種 | スーパーマーケット、ドラッグストアー、百貨店、デパート、駅ビル、店舗、ショッピングモール、飲食店、ケーキ店、酒屋、介護施設、病院、社員食堂、問屋、精肉店、パン屋、配送センター、老人ホーム、保育園、オフィス、銀行、ラーメン店、洋菓子屋、和菓子屋 |
適格請求書発行事業者登録番号:T8030001022586
資格:準中型免許、整備管理者、フォークリフト、中型免許、運行管理者
会社沿革
| 1971年 | 創業1971年1月26日 埼玉県戸田市に軽自動車での配送業務をスタート 社名:セイリョウ運送 |
|---|---|
| 2000年 | 一般貨物自動車運送事業 取得 |
| 2000年 | 貨物運送取扱事業 取得 |
| 2001年 | 資本金300万円 有限会社 セイリョウ運送 設立 代表取締役 青木 勇 就任 |
| 2005年 | 戸田営業所開設 |
| 2006年 | 動体管理(デジタル・タコメーター)「TRU-SAM」導入 |
| 2006年 | 「業務部」 「営業部」 設立 |
| 2007年 | 代表取締役 青木 勇 退任 |
| 2007年 | 代表取締役 小林 良子 就任 |
| 2008年 | 資本金700万円増資 株式会社 セイリョウ 設立 |
| 2009年 | 介護事業部 設立 |
| 2010年 | 経営革新計画 承認 動体管理(デジタル・タコメーター) 「みまもりくん」導入 |
| 2013年 | 代表取締役 小林 隆文 就任 |
| 2016年 | 戸田蕨トラック協会 入会 |
本社・営業所について
営業所は2022年現在、埼玉県戸田市と千葉県市川市の二ヶ所で営業しています。
主に戸田市の営業所で業務・管理などを行っております。
事務所内は部署ごとに分かれています。
配送課・総務人事課・介護課・システム課で分かれていて、
会社で用意されたクラウドを活用しながら様々な業務を行っております。
2020年に蔓延したコロナウィルスの時も、
自社のクラウドを活用しリモートでの業務を行う事ができました。
この様な予測のできない事態や災害などが起きた場合でも、
事務所が完全に停止しない様にクラウドやリモートに対応できるような仕組みを常に考えています。
2021年に2階が増設され事務所の使い方も多種多様になってきました。
2階では移動式のテーブルと大きな液晶ディスプレイが設置されているので、
使用したい内容によってレイアウトを変えて、
様々な用途での活用の仕方が可能となっています。
例えば、社員全員を集めた全体会議やリモートで映像を流しながら研修を行ったり、
または社内での勉強会を行ったりと様々な使用方法があります。
また千葉営業所には事務所が設置されていないので、
そちらの管理も全て戸田の営業所で管理しています。
本社は埼玉県戸田市新曽にあり、現在のスタッフは社長と経理主任のみとなっています。
笹目の営業所ではできない重要な処理を本社では行っています。
本社と営業所で連携を取りながら
現場がスムーズに業務が進むように管理を行っています。
デジタコ搭載
弊社ではデジタコを全車両に搭載しています。
全ての運行データを管理センターに集約し
解析するクラウド型のシステムを活用しています。
車両と事務所をつないで、リアルタイムの高度な運行管理を行っています。
インターネットに接続したPCからいつでも管理ができ、

「運転日報」「車両の追跡」「ECO安全運転レポート」など
様々な情報を簡単に一覧する事ができます。
全てクラウドでの管理なので必要な時に欲しい情報を
タブレットやスマホからも確認する事ができます。
またトラックに搭載されているデジタコは
「速度」「エンジン回転数」「急減速」「急加速」などの
設定も細かく決める事ができます。
ドライバーが無理な運転をしてしまった場合は、
音声で注意喚起をしてくれるので
しっかり安全運転を意識しながら運転に集中する事ができます。
車両紹介
弊社で使用している冷蔵・冷凍トラックの紹介をしていきます。
軽の冷蔵・冷凍トラック
弊社では軽の冷蔵・冷凍トラックが3台あります。
小型車なので狭い場所でも問題なく入って行く事が可能です。
都内や駅前、または天井が低い倉庫など、トラックではなかなか止めづらい場所に
使用して行く事が多いです。
軽トラックを使用していた事例としては
冷蔵品は
野菜・お酒・お菓子・惣菜・介護食品・パンなどの配送になります。
冷凍品は
ケーキ・アイス・ジェラート・加工食品・スープ・惣菜・
冷凍食品などの配送になります。
荷台は小さい造りにはなりますが
温度の方は冷蔵であれば5度から10度
冷凍であればマイナス20度まで下げる事ができます。
温度管理は運転席で設定できます。
ご要望の温度帯によってドライバーが設定し冷凍機を回していきます。
軽トラックの荷台の大きさは
高さ:100cm 横:125cm 奥行:165cm
例えば箱の大きさが
40cm × 30cm × 30cmの場合であれば
縦・横共に4列で3段ずつ積み上げられる計算になるので
48ケース積むことができる計算になります。
ただ、冷凍機が荷台の内側に出っ張って付いているので その部分は荷物が当たってしまうので、積み上げることができません。
その部分は荷物が当たってしまうので、積み上げることができません。
その分は約2ケースのスペースが必要となるので
配送可能となる量は48-2=46ケースとなります。
運ぶ箱の大きさで
数は変わってきますが目安にして頂けたらと思います。
冷蔵・冷凍トラック
弊社では2tと3tの冷凍・冷凍トラックが12台稼働しています。
軽トラックとは違って
運ぶ事の出来る量が大幅に増えます。
一日に何件も運ぶ事が出来ますし
一気に何百ケースも配送することが可能です。
箱の大きさにもよりますが一日に1000ケース運ぶ事もあります。
冷凍機も大きく

冷やすパワーが強いので短時間で冷凍状態にできます。
荷卸しの際は、扉を開けるので外気が入ってしまい
温度は多少上がってしまいますが
すぐに扉を締めれば元の冷凍状態に戻す事ができます。
また荷台に中扉が付いているトラックがいくつかあります。
そのトラックを使用する場合 冷凍品と冷蔵品を一度に配送することが可能となります。
冷凍品と冷蔵品を一度に配送することが可能となります。
その場合は、相談して頂けたらと思います。
荷台の大きさが少しずつ違うトラックもあるので
内寸をいくつか載せたいと思います。
参考にして頂けたらと思います。
①3t冷蔵・冷凍
高さ:1810mm 幅:1900mm 奥:4430mm
②3t冷蔵・冷凍
高さ:1770mm 幅:1880mm 奥:4430mm
③3t冷蔵・冷凍 高さ:1830mm 幅:1880mm 奥:4430mm
高さ:1830mm 幅:1880mm 奥:4430mm
④3t冷蔵・冷凍高さ:1950mm 幅:1750mm 奥:4570mm
⑤3t冷蔵・冷凍
高さ:2200mm 幅:1950mm 奥:4320mm
荷物の積み方
荷物の積み方は、運ぶものの形や大きさ運ぶ形式に寄って異なります。
積み方・卸し方にはいろいろな方法や種類があり、
普段聞き馴染みが無い言葉だと思いますので
こちらでいくつか紹介していきたいと思います。
バラ積みバラ卸し
こちらの積み・卸し方は、引っ越しする時などにも見る事ができる、基本的な積み方です。
段ボールの箱を綺麗に積み上げているのを一度は見た事があると思いますが
まさにあの積み方です。
倉庫でまとまった荷物を荷台へ運んでいき一つ一つ積み上げていきます。
この積み方は、ドライバーの手で一つずつ積み上げていくので
荷物の個数が多い場合は、大変に感じることもあるかもしれません。
ただ、セイリョウでは20kg以下の荷物に限り
バラ積みバラ卸しにしてもらうように取引先にお伝えしていますので
数が多くて重いというパターンはありませんのでご安心ください。
カゴ積みカゴ卸し(長台車)

こちらの積み・卸し方は、カゴ台車と言う、文字通りカゴ型になった大きな台車に荷物を入れた状態で、台車のまま荷台に積んでいく方法になります。
スーパーなどに食品や水などを持っていく時によく活用されます。
カゴ台車にはたくさんの荷物が積んであります。
これをバラバラに積むと大変ですが、カゴ台車ごと荷台へ運んでいけるので
少しの力で荷物を動かすことができます。
ただ、台車自体はとても重くなっているので
うっかり荷台から台車ごと落としてしまうと大惨事になってしまいます。
慎重に扱わなければなりません。
重量物の積卸し
こちらの積み・卸し方は、業務用の冷蔵庫や食品売り場のショーケースなどといった
重量のある機械を運んでいきます。
一人でできる作業ではないので、二名以上で協力して積み込みしていきます。
大体の場合、荷物がたくさんあるというよりは
大きなに荷物が一つだけあって運んでいくという流れになります。
大きくて繊細な機械を運んでいくことが多いので
運転や積卸の際は、いつも以上に注意していく必要があります。
無駄な待機時間の見直しで生産性アップに
仕事をするにあたって時間は有限です。
勤務時間内に、業務や作業は複数項目あり、それを決められた時間にこなしていかなければなりません。
それができない場合、作業や仕事を次の日に持ち越したり、取らなくてもよい残業の時間が発生したりしてしまいます。
本当に仕方のない場合もありますが、実は仕事の動きを細かく分析してみると、無駄な時間の使い方をしている部分も見えてきます。
それは株式会社セイリョウの配送業の中にもありました。
弊社でも、必要のない残業が配送業の中にもたくさんありました。
配送業は会社から会社へ品物を運ぶ仕事です。
荷物の積み下ろしや運送中などが業務の大半です。
マンパワーやテクニック、荷台の工夫などをして、時間のロスを少なく、素早く業務をこなせるように努力をしてきました。
しかし、その時間以外にも大きな時間のロスがありました。
それは“待機時間”です。
待機時間というのは、文字通りトラックの中でスタッフが“待機をする”ということです。
これはどのような時に起こるかというと、荷物を出し入れする倉庫が開かない時に発生します。
この原因は主に、倉庫を持つ相手のキャパオーバーにより発生します。
倉庫が開かずに何台ものトラックが、荷物を出し入れできずに待っている状況です。
この時間にも、もちろん人件費が発生しています。
現在は、環境のことも考え、アイドリングストップを心掛けていますが、やはりガソリン代も多く発生しています。
多少のイレギュラーな時間のロスであれば、仕事ですからしょうがないなという気持ちはありますが、
申し出があった時間に弊社のトラックが伺っても、そこから数時間待たされる時もあります。

そうすると、もちろんその荷物を運ぶ先にもご迷惑が掛かってしまいますし、次に控えている業務にも支障が出てしまいます。
このような待機時間は配送業では昔からあり、「配送業では当たり前」「待機時間を渋っていては仕事がなくなる」という考えから、
この問題は配送業をする企業の中でも放置されがちな内容です。
そんな中、株式会社セイリョウでは、約6年前から待機が発生する場合は待機料をいただくことを始めました。
きっかけは弊社の配送業スタッフが、そのことに対して悲鳴を上げていたことからです。
配送業の仕事は常に人手不足です。それにもかかわらず業務はてんこ盛り。
そこに長時間の待機時間も加わってしまうと、現場は悲鳴を上げずにはいられません。
さらに先ほども書いた通り、ガソリンも捻出するので、その分経費もかかってきます。
このような現状を打破するべく、待機時間が発生した場合「待機時間料」も請求させていただくことにしました。
そのようにした結果、何もしていない時間を減らすことができ、生産性も上がりました。
1日の勤務で、よりたくさんの業務をこなせるようになりました。
株式会社セイリョウでは「トラックに乗っている時間を1台ずつ短くして生産性をあげていこう」
という考えで配送業務を行っています。
それは業務内ではメリハリをつけて、無駄な時間ロスをなるべく避け、効率よく仕事を進めてゆくという考えからきています。
そうすることにより、生産性を上げるばかりではなく
“勤務時間内に業務を終える”という当たり前のことが、確実に実現できるからです。
昔は“配送業は残業が当たり前”という考えがありましたが、
業務一つひとつを意識していくことで、その負の考えもなくしていけるのではないかと考えています。
庸車・協力会社様の募集

国土交通省主催「企業交流会」に参加
2023年1月に行われました、国土交通省主催の「ホワイト物流」推進運動
埼玉県「業界・業種セミナー」での「企業交流会」にて
弊社の取り組んでいる仕事内容や活動内容を説明させて頂きました。
運送業界全体のイメージはどうしても「労働時間が長い」「厳しい環境」など
少しマイナスに感じられることが多いですが、
会場又はZoomで集まった皆さんと交流を深めながら
運送業界にいる事で「こんなことを学ぶことが出来る」や「こんな効果がある」といった内容を
自社の視点から説明させて頂きました。
交流会の中で質問を受ける時間がありました。
印象に残っている質問の中で4つご紹介したいと思います。
1,セイリョウでの女性の活躍の割合はどのくらいですか?
2,運送業で面白い事は何ですか?
3,セイリョウの強みはなんですか?
4,年齢の割合はどのようになっていますか?
セミナーの中で興味を持って頂いた質問ですので、
こちらのホームページを観た方も興味をお持ちかと思います。
実際に応えさせて頂いた内容を載せますので、是非参考にして頂けたらと思います。
1,セイリョウでの女性の活躍の割合はどのくらいですか?
弊社では社員さんが1名、準社員・パートが4名働いています。
社員の1名は、2022年の4月に入ってきた19歳の新入社員さんです。
学生の頃から配送に興味を持っていた様で、学校で運送のパンフレットを見て
セイリョウに興味を持ってくれたそうです。
とても明るく前向きな性格で、現在も日々配送のスキルを磨いています。
準社員・パートの4名ですが、皆さん事務所で業務を行っています。
皆さん、お子さんを保育園や学校に預けてから、セイリョウでの業務を行っています。
準社員やパートという立場ですが、配送課・総務課・人事課とそれぞれ役割を持って仕事をしているので、
責任感や達成力がとても高い皆さんが集まっています。
セイリョウ全体では40名ちょっとなので、女性の割合は少な目ではあります。
ただ、女性の方が元気があって会社を内側から支えている方ばかりです。
現場の男性陣は朝から配送に出ていくので、
疲れて管理の方に意識が向かないドライバーさんも中にはいます。
そんな時に事務所のパート・準社員の皆さんが、サポートしていきながら一緒に考えていき
そこからチーム力に発展していっています。
セイリョウにとって、女性の活躍はとても重要な力となっています。
2,運送業で面白い事は何ですか?
運送業で面白い事は、考える力が身に付くという所です。
配送先が毎日変わる業務や荷物の形や大きさが違う現場にいく様になると、
少ない情報の中で配送ルートを考えたり、荷物の持ち方を微妙に変えてみたり、
どの様な段取りにすれば効率よく積み卸ができるかなど、
様々な事を現場で考えていきます。
ドライバーさんは現場に出ると一人にで作業をしなければなりません。
合っているか間違っているかを自分ひとりで判断する事が必要になってきます。
1人での作業が多くなっていくからこそ、
自分から動く行動力が身に付き、判断力も素早くなっていきます。
更にセイリョウでは、ドライバーさんがそれぞれ身に付けたスキルや現場の情報、商品の扱い方など
会議で話し合う時間を作っています。
1人での現場であるからこそ、自分ひとりのルールが強くなってしまう場合があり
その場合なかなか全員が意識を同じ方向に向ける事が難しくなっていく事があります。
その状態をなくしていく為、定期的にドライバーさんには集まって頂き
現場の状況や作業効率を上げる方法を皆で話して情報交換をしていきます。
またこれを行う事によって、『独りではない』と思う事ができます。
現場に一人で行くからこそ考える力が身に付きますが、
孤独を感じやすかったり意識のズレが発生する事があるので、
セイリョウではドライバーが集まる時間を大事にしています。
3,セイリョウの強みはなんですか?
弊社の強みは、助け合いがあるところです。
先程も書かせて頂きましたが、ドライバーという仕事は孤独になってしまう部分があります。
その原因としては出発時間も皆さんバラバラで、帰ってくる時間もバラバラなので
同じ時間を共有する事ができず、自分勝手な行動や他人事になってしまう事が昔のセイリョウではありました。
その状況を変える為にセイリョウでは、
新入社員にはメンターをつけて毎月1回は必ず面談を行っています。
上手くできた事や失敗した話、気持ちの面や目標設定など、メンター役が聴きながら寄り添っていく事で
お互いに信頼関係がうまれ自分事プラスアルファの部分も考えられる人材が育つ環境が整ってきました。
また、会議においてもトップダウンで指示をするだけではなく、
「どのようにしたら皆で目標実現ができるか?」と一緒に考える時間を作る事で、
協調性や助け合いの重要性を学ぶ事ができています。
例えば、一人の現場で分からない事があった場合、スタッフ間で信頼関係ができていなければ
質問をする事ができません。
ただ、現在のセイリョウでは面談や会議でお互いをする時間を作っていく事で信頼関係が生まれ、
分からない事は質問できるようになり、困っているスタッフが居たら声をかけられる様になっていきました。
先輩は新人の皆さんを巻き込み、新人の皆さんは先輩に質問をしていく事で
独りで仕事をしているのではなく、皆で一緒に仕事をしているという意識が高まっています。
お互いに助け合える職場こそが、セイリョウの強みです。
4,年齢の割合はどのようになっていますか?
セイリョウでは、幅広い年齢層によって構築されています。
社員・準社員・パート全ての割合は
20代 5%
30代 5%
40代 28%
50代 22%
60代 23%
70代 17%
60代・70代のパートさんの割合が圧倒的に多いです。
これは弊社の代表 小林がシルバー人材の活用に力を入れているからです。
まだまだ働くことが出来るのにに働く場所がないという
60代以上の皆さんに光をあてて、もう一度セイリョウで輝いてもらいたいという
社長の想いからシルバー人材の活用がスタートしました。
今では、60代・70代のパートさんが現場に向かい
40代・50代が現場と管理を行い
20代・30代は学ぶ場
として、自然と年齢で役割が明確に分かれてきています。
年齢の幅が広いからこそ、助け合いや歩み寄りが生まれ
社内で楽しく話している場面が沢山あります。
この年齢の幅こそ、チーム力を上げる秘訣なのかもしれません。
人材確保・育成のセミナーで登壇しました
地域密着の人材確保のセミナー参加
2025年3月18日に行われた、
戸田市商工会と武蔵野銀行連携セミナー
『地域密着の組織づくり専門家が語る
「最低賃金引き上げを迫られるなかでの人材確保とは」
~地元企業の採用と定着~』に、
社長の小林が登壇しました。
このセミナーは、
中小企業診断士の坂上成人先生を講師に迎え、
人材確保の難しい現在、
どのようにして人材不足を解消するか、
どのように人を採用していくかなどを
学んでいく内容でした。
小林は坂上先生の講演の後に、
「人材育成を積極的に行っている企業」の一例として
発表をさせていただきました。
セミナーに参加された方の人数は約30名。
その方々の前で約20分の発表時間をいただき、
株式会社セイリョウが培ってきた、
人材育成の概要を発表させていただきました。
人材採用と育成について①:以前と現在のセイリョウの違い
まず、本題に入る前に、
以前のセイリョウはどんな印象だったのかを見ていただきました。
映し出されたPowerPointには、
以前の会社の雰囲気を表した写真が貼られています。
写真は2006年頃の写真で、
それはどこか怖い印象を与えるスタッフ達の写真でした。
まだ、人材育成に力を入れる前の写真で、
写っているのは退職したスタッフ達です。
当時採用されたスタッフの中には、
入れ墨を入れていたり、
反社会勢力と関係があると自らが公言したりと、
かなり危なっかしさを感じるスタッフも働いていました。
仕事でもわがままし放題でした。
次に映し出した写真は、
それと対比した全員おそろいの作業着を着て、
笑顔で並ぶ2025年現在の写真です。
約20年の間に、
株式会社セイリョウがどれだけ
人材育成に力を入れてきたかがわかる写真だと思います。
怖い印象を与えた2006年の写真の頃には、
「社長の想いとは反対の想いで組織が動き出してしまう」
「事故、修理、故障が多い」
「報連相ができない(嘘をつく)」など、
さまざまな問題が起こってしまっていました。
人材採用と育成について②:セイリョウの人材採用
この人材不足の時代に、
セイリョウで力を入れているのは、
インターネット内のコンテンツの活用です。
それを大きく3つに分類すると以下になります。
1つ目は「Webの活用(HP)」です。
冷凍冷蔵のセイリョウと介護タクシーのHP、
セイリョウ採用サイト、
マイビジネス(配送、介護、型付け屋)を運用しています。
それも、現在のWeb形式に沿った
見やすいカタチに作られています。
そんなの当たり前かと思われるかもしれませんが、
現在でもひと昔もふた昔も前の
デザインのHPを運用している企業を見ます。
それを見たお客様は、
この会社は運営しているのだろうかと
不安になりますし、
新規のお客様が寄り付かない可能性の方が高いです。
特にHPは成功事例やブログのような記事を毎月更新して、
常に新しい情報を発信しています。
発信し続ける事で、
株式会社セイリョウをより知ってもらうことができますし、
この会社はしっかりと“動いている”
ということをわかってもらうことができます。
2つ目はSNSです。
現在Instagram、YouTube、Facebook、Xの4つを運営しています。
こちらも、頻繁に更新をしています。
特にInstagramは、
平日に欠かさず会社全体の取り組みや
雰囲気がわかる投稿していて、
月1で仕事とは関係のない社長ネタ、
さらに有料動画広告を上げて盛り上げています。
毎日の投稿の甲斐があって、
フォロワーも徐々に増えていきました。
また、XとFacebookはそのInstagramに繋げて、
より株式会社セイリョウに
興味を持ってもらえるように投稿を続けています。
3つ目はネット求人です。
DOMO!net、ハローワーク、アルバイトタイムスで、求人広告を出しています。
人材採用と育成について③:続ける事、そして最後にはHPへ
この3つを運用していますが、
ポイントとしていることは
「とにかく続けること」
「最終的にはHPにユーザーを誘導する」という考えです。
お客様がそのSNSのアカウントを見た時に、
1日前、3日前などの直近で更新されていれば、
その会社はしっかりと“動いている会社”なのだとわかっていただけます。
しかし、1年も更新がない場合は
「この会社は大丈夫だろうか?」と不安を与えてしまいます。
とにかく続けることが運用のポイントです。
さらに大切にしているポイントは、
SNSのFacebookやXでは
Instagramに行き、
その後HPへ飛んでもらえるように。
求人広告では、
InstagramやHPに跳んでもらえるように、
と考えてアップしています。
SNSも株式会社セイリョウのことを
知ってもらうコンテンツではありますが、
HPが一番会社のことを知ってもらえると考えています。
さらに、求人HPにも飛べるバナーも設置しているので、
弊社に興味のある方はそこにも簡単に向かうことができます。
人材採用と育成について④:セイリョウの人材育成
いくら求人を入れても、
入社後の人材育成をしっかりしないと、
人はすぐに出ていってしまいます。
セイリョウでは、
約20年の時間を費やして、
以下の事を活用して人材育成に努めています。
1つ目はお互いの信頼関係を築き、
個人やチームの可能性を広げていく「コーチングの活用」。
2つ目は、現場のマニュアル、
事務のマニュアル、研修などを動画で対応する「動画の活用」、
3つ目は毎朝8:45から15分間承認し合う場を作る「朝礼の活用」です。
これらを活用していった結果、
会社全体の雰囲気が大いに良くなりました。
また、少しの変化ではありますが、
会議の参加率が上がり、事故数も半分、売上も約1,400万円も増えました。
この変化は、試行錯誤しながら人材育成を続けていった結果だと思います。
この3つの活用によって、
株式会社セイリョウのビジョンである「もの(者・物)が活躍できる職場」へと、
成長し続けていると考えています。
補足として…
ここまでが事前に用意した資料に沿って
発表させていただいた内容です。
最後に小林は、
「弊社のT課長のようなスタッフを増やしたい」と加えました。
幹部のTさんは、
会社の中では中枢の仕事を担っている
重要な人材ではありますが、実は準社員なのです。
なぜ正社員でないかというと、
彼にはダンサーとしての人生があるからです。
株式会社セイリョウのために、
昼夜休日問わず働かなければならないというのは、
会社の利益に繋がる可能性はありますが、
その人の人生を狂わせてしまいます。
社長の小林が心に留めるのは
「会社のビジョンのために
その人の人生を壊わしてはならない」ということです。
小林はTさんのような働き方のスタッフを、一番望んでいるのです。
今後も発表の場へ
社長の小林は今回のセミナーの経験を機に、
より株式会社セイリョウの
取り組みを知ってもらいたいと考えるようになりました。
この約20年で株式会社セイリョウが培った人材育成の方法、
試行錯誤した歴史、成功事例、活用したツールや技術など、
1つの会社が大きく成長した材料がたくさんあります。
それをどんどん発信していきたいと考えています。
運送業の経営セミナー、企業の人材育成セミナー、学校の就職セミナーなど、
さまざまな場所に足を運んで株式会社セイリョウの歩みを発信し、
企業成長の材料、就職活動の材料などに
活用いただけたら嬉しいなと考えています。
運送の中小企業がここまで変化し続けた事は、
運送業界にも大きな成功材料になりますし、
これからの運送業への未来にも大いに役に立つと考えています。